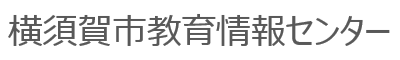はじめに
| トップページ | はじめに | 児童・生徒の作品 |
| 子ども科学賞・発明展 | サイエンスサマー | 奥付 |
は じ め に
(保護者・教職員の方々へ)
横須賀市教育研究所では理科教育を推進しており、子どもと直接関わる事業として、年8回開催される土曜科学教室や、夏休みに開催されるサイエンスサマーを実施しています。毎回、多くの応募があり、周りの参加者と協力して、実験や観察に取り組み、たくさんの発見をしています。
横須賀市小学校児童・中学校生徒研究集録は、
1.課題解決に向けて予想や仮説をもち、それらを基にして観察や実験を行うことや結果に対する考察などを通して、問題解決しようとする力を養うこと
2.結果に対する考察などを表現する中で、自然の事物・現象についての考えが、少しずつ科学的なものに変容していくことを目的に実施しています。
今年も、土曜科学教室やサイエンスサマーに参加した小学生の作品をはじめ、市内の小学生・中学生が夏休み中に取り組んだ自由研究の中から、学校代表として選出された作品を研究集録にまとまめました。
本研究集録の作成にご協力いただいた各校の先生方に感謝を申し上げますとともに、熱心に研究に取り組んだ児童生徒のみなさんの努力と保護者の皆様の支えに敬意を表します。
(小学生・中学生のみなさんへ)
自由研究とは、「なぜだろう」、「不思議だな」という思いをもとに、「調べたい」、「もっと試してみたい」、「実現したい」ことについてテーマを決め、じっくり取り組むことです。自由研究では、予想や仮説を立て、調べる方法を考えるなど解決への見通しをもち、実際に観察・実験をし、結果を記録します。そして、結果をもとに考察し、結論を導いていきます。この一連の過程は、社会において求められる「問題解決の力」を身に付けることにつながります。
さて、みなさんは「国際宇宙ステーション(ISS、以下ISS)」について、知っていますか。今年9月まで船長をしていたのは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙飛行士「大西 卓哉」さんです。
ISSでは、たくさんの国の人たちが協力し合って、宇宙における特殊な環境を利用して様々な実験や研究を行っています。地球では、ISSで宇宙飛行士達が実験や研究できるように、多くの人が24時間体制でサポートしています。その他にも宇宙での生活に必要な物資、実験装置、定期交換部品などをISSへ届けるため、打上げ機が運用されています。つまり、ISSでの実験・研究には世界中の人が関わっていて、全力で研究を支えています。
研究で最も大切なことは「あきらめない」ことです。多くの人が助け合って研究を行い、小さな研究の積み重ねと新たな疑問や発見、解決に向けた観察や実験を繰り返すことで、謎が解き明かされていきます。また、自分一人では困難でも、さまざまな人との関わりの中で分かることや明らかになることがあります。今年、研究集録に取り組んだみなさんが、これから困難に直面してもあきらめず取り組み続けることを願っています。
横須賀市教育研究所長 杉戸 美和
更新日:2025年11月28日 15:00:00