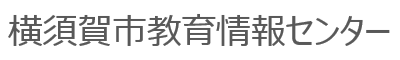月報 2003年度 7月号
平成15年(2003年)7月1日
編集発行・横須賀市教育研究所/代表・五ノ井文男
〒239-0831 横須賀市久里浜6-14-3
TEL(046)836-2443(代) FAX(046)836-2445
巻頭
経験との付き合い方を考える
|
ある心理学者が次のような実験を行いました。
一匹の犬を柵に入れ電極をつなぎ、ランプを点灯させてから犬の体に電流を流してショックを与えます。犬はショックから逃れるためにいろいろ試行錯誤を始めます。そこで犬が柵を跳び越え、外に出た時点で電流を切ることとします。
このことを何回か繰り返すと、犬は電流を流さなくとも、ランプがついただけで柵を跳び越えるようになります。
次に、ランプが点灯し、柵の外に出た段階で電流を流すようにします。犬は電気ショックに驚きます。しかし、次の回以降も柵の外に出るたびに電気ショックを受け、それでも跳び越えることを止めません。
やがて心理学者は、あることに気づきました。犬が、点灯と同時に柵を跳び越えようと、必死に努力しているかのように見えたのです。
「柵を跳び越えたなら安全なはずだ。しかし、それでもショックがきたのは自分の努力が足りないからだ。もっと頑張って素早く柵を跳び越えるようにしよう」
と考えているかのようです。
このことから心理学者は、次のような考察をしました。いったん危機回避行動を覚えると、状況が変わってそれがどんなに時代遅れの方法になっても、それを手放そうとはしない。これは人間にも当てはまることなのではないか、と。
作家、俳優、演出家でもある中谷彰宏さんは、企業で講演するとき、「過去の、特に成功体験を忘れることが大切である。もう時代は変わったのだという認識をもって、学習よりも、学習したことを忘れる(脱習)をしなければいけない。」
という趣旨のことを話すそうです。
|
確かに人は、自分の原体験をテキストにして現在の思考や行動を決定しているのだと思われます。そして、そこから抜け出しにくい存在でもあります。特に、過去の成功体験は、無意識のうちに踏襲しがちになるのではないでしょうか。
実際に、新しい企画を立案するとき、自分の過去の経験が邪魔になることがあります。新年度が始まるとき、「例年どおり」という流れの中で、これまで変わらなかった目標や方針が、他校から転勤してこられた先生のひと言によって、再検討される場合があります。
「変化の激しい社会にあって……」という表現は、既に使い古された感があります。そう感じるのは、事実それだけ昨今の変化が急激であり、そのことを誰もが認めているということに他なりません。そして、この変化の激しい社会を生き抜く子どもたちに求められている力は「自分で課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力……」ですが、その力はむしろ私たちに求められているのかもしれません。
敢えて昔のことに言及するならば、かつての学校は地域にあって最新の設備であり、最新の情報を提供する場でした。「例年こうしている」、「前回までは……」、「昔はよかった」では通用しない今、原体験の成功経験の全てを否定するというのではなく、その活用をどのように見極めるか、変革の時代にあって、そのバランス感覚が大切なのだと考えます。
(指導主事 木屋 哲人)
|
▲TOPに戻る
特集
| ■■ これからの進路指導 ■■ |
|
「行ける学校から行きたい学校へ」
池上中学校 教諭 栗原 裕
高校の入試選抜が多様化し、生徒・保護者は勿論、指導する先生方も戸惑うことが多くなったと思います。
今までは成績を中心に決められた学校選択。これからは多様な幅の中から「行きたい学校」として考えさせることが第一ではないかと考えます。受け入れる側もそれぞれの特色を出し、努力されていることを感じます。新しくできた総合学科や単位制の普通科については、教師もその中身を十分知ることが大切です。正確な情報を持ち、それらを生徒に知らせることは不本意入学をなくすことにもなります。
情報を早めに提供したり、自らの行動を迫っても、生徒の意識を早くから高めることは難しいものです。自分で切り開く進路だという意識を持たせ、常に働きかけることが必要です。
新しい学校には期待が集まり、希望が集中します。しかしその3年間をきちんと理解し、3年後の自分が想像できている者はどのくらいいるでしょうか。
試行錯誤した「行きたい学校」、結果的には「選抜」されることになります。課題もありますが、このシステムを有効に活用できる進路指導が求められているのです。
就職希望者への求人も激減しています。好景気の頃には、高卒が採れないので採用幅を広げたいという事業所がありました。
今までの指導にとらわれないための学習・研修を重ね、まずは教師の意識改革です。生徒・保護者もよりよい選択ができ、高校(中学校卒業後の進路)は人生の通過点だという気持ちの余裕を持たせたいです。
|
「総合高校の総合学科における
これからの進路」
横須賀総合高校 校長 熊谷 和久
本年4月1日、本市唯一の市立高等学校として総合学科を有する学校、市立横須賀総合高等学校を開校しました。
総合学科とは、「生きる力」を養う学科です。現代の子どもの社会的成長のスピードの遅さや、先行きの不透明感から考えると、高校進学時に自分の卒業後の進路を決定することは難しいことです。そこで総合学科では、入学してからじっくりと自分の将来の進路を考えてもらえるように、カリキュラムが考えられているのです。
その一つが1年次で履修する「産業社会と人間」という科目であり、もう一つは2年次からの選択科目です。
「産業社会と人間」という科目を1年間履修することで、様々な分野の社会人の話を聞き実務作業を体験し、自分の適正を考えます。そして、2年次以降では進路に沿った科目を自己選択し自己責任で履修するのです。勿論、大学受験に必要な科目のみを選択し、研究職や医師、上級国家公務員になることもできます。
選択科目は全日制・定時制合わせて200以上あり、2年次以降に履修します。選択科目は系列で選ぶことも、様々な系列分野をまたいで選ぶことも自由です。こうして自己責任で選択したオンリーワンのカリキュラムで自分の進路探しをできるのが総合学科の特色です。
命ある限り尽きない人生の旅では、総合学科で学んだ自分探しの術(すべ)が、様々な局面で活かされてくるものと確信しています。
|
▲TOPに戻る
相談セクション
| 孤立させない関係づくり |
|
「隣家の中学生が、もう1年近く学校へ行っていないようです。外出もほとんどしないのでとても心配しています。平日の昼間は中学生ひとりきりで、家の中でどうしているのでしょう。隣人として何かできることはないのでしょうか。」中年の女性の声で、このような電話相談が寄せられました。
不登校の子を持ち悩まない親はいない、つらいからこそお隣にも言えない、保護者を支えることが間接的にお子さんを支えることになる、性急に不登校の話題に入らずにあいさつや何気ない会話から始めてみてはいかがでしょうと、まずお隣と親しくなることを勧めてみました。
後でよく調べてみると、この中学生は以前に相談を受けていたケースでした。隣人だという女性が、多少批判的に語っていたその中学生の保護者は、たいへん悩んでおられ、面談室でよく涙ぐんでいたことを思い出しました。隣近所とはいっても、なかなか家の中の心配事は他人には話しにくく、本当の心情は理解されにくいものです。
隣人の女性は、中学生のことを心配しながらも、心を開いてくれない隣家の住人に寂しさを感じていたのかも知れません。それにしても、家族以外の方が、わざわざ電話をかけて相談してくれたという事実に、嬉しさを感じました。大勢の目が注がれているということが、助け合いの第一歩です。
他人の生活には感知しないことが常識になりつつある現代社会においては、困っている人を孤立させない善意ある関係作りが求められています。
学校内においても、孤立した児童・生徒を出さないような集団作りが大切です。子どもが集団から孤立するもっとも深刻な原因は、「いじめ」による無視や差別です。「いじめ」に関しては、全国や県、あるいは本市でも、近年発生件数は減少傾向にあります。各学校での「いじめ」根絶にむけての取り組みが、実を結んできているのだと思います。「いじめ」はいけないことだ、という意識は子どもたちの間に確実に育ってきています。
|
しかしその一方で、内気で自己表現が苦手だったり、反対にはしゃぎすぎていたり、ほんの少し他の子どもと雰囲気が違うといった子どもに対して敏感に反応し、関わりたがらなかったり、積極的には友達になりたがらない傾向が、子どもたちの中に依然として強くあるような気がします。「いじめ」がない集団が、必ずしも暖かな感情でつながれた豊かな人間関係を作っているかといえば、そうとは言い切れません。
多くの不登校相談の中から語られる学校生活は、無味乾燥なものです。人から嫌な事を言われたりされたりしたことはないが、楽しいことも何もないというような事をよく聞きます。同じクラスの子どもの名前を何人知っているか、確かめたところ3、4人しか答えられなかった不登校児がいました。その子は「他の子のことはよく知らない、気の許せる友達はいない、他の子はみんな仲良しグループに入っている。」と言っていました。遊びを通して社会性が育つ大切な時期に、孤独感を感じていなければならない子どもは不幸です。
大人と同様に、子どもにもいろいろな悩みがあって当然で、小さな胸を痛めることがありますが、一緒にいるだけで楽しいような大好きな友達が周りにいたなら、大概のことは乗り越えられるのではないかと思います。
似たような個性の子どもたちは放っておいても仲間になります。違う個性の子どもたちを、生き生きとした学級集団としていかに育てあげるかが、教師としての腕の見せ所ではないでしょうか。
(指導主事 下川紀子)

|
▲TOPに戻る
研修セクション
|
平成15年度 夏季研修講座一覧
| 記号 |
講 座 |
講師 |
所 属 |
講座内容等 |
日程 |
会 場 |
| A-1 |
夏季大学 |
岡本
薫 |
文化庁長官官房 著作権課長 |
学校と著作権 |
7.22 A |
文化会館中ホール |
| A-2 |
夏季大学 |
山上
隆男 |
都立つばさ総合高等学校 校長 |
特色ある学校づくりをめざして |
7.24 A |
文化会館中ホール |
| A-3 |
夏季大学 |
佐藤
千穂子 |
北里大学病院精神神経科心理室臨床心理士・医療衛生学部講師 |
児童虐待とその予防、早期発見と心のケア |
7.24 P |
文化会館中ホール |
| A-4 |
夏季大学 |
福田
紀子 |
国際理解教育センター |
人権・同和教育に係わる今日的課題 |
7.28 A |
文化会館中ホール |
| A-5 |
夏季大学 |
奥寺
康彦 |
教育委員会委員長 |
サッカーを通した人材育成 |
7.29 A |
生涯学習センター |
| B-1 |
国語 |
鶴田
清司 |
都留文科大学 教授 |
文学的な文章の指導のあり方 |
7.28 P |
第1研修室 |
| B-2 |
国語 |
市毛
勝雄 |
日本言語技術教育学会 会長 |
確かな学力づくりを目指して |
7.30 A |
ヴェルクホール |
| B-3 |
国語 |
卯月
啓子
|
野田市立南部小学校 教諭 |
生活に役立つことばの力をつける学習の場づくり |
8. 4 P |
第1研修室 |
| C-1 |
社会 |
山本
詔一 |
横須賀開国史研究会 |
開国の街 よこすか |
7.28 A |
ヴェルクホール |
| C-2 |
社会 |
杉山
哲也 |
秦野市立広畑小学校 教諭 |
子どもが生きる社会科授業の実際 |
8. 1 A |
第1研修室 |
| C-3 |
社会 |
澁澤
文隆 |
信州大学 教授 |
生きる力を育てる社会科授業 |
8. 4 A |
ヴェルク第1会議室 |
| D-1 |
算数・数学 |
森
昭夫 |
横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校 教諭 |
はじめに子どもありきに根ざす鎌倉小の学習 |
7.29 A |
第1研修室 |
| D-2 |
算数・数学 |
吉田
映子 |
東京都中野区立桃丘小学校 教諭 |
算数・数学的活動を活性化する教材教具の工夫 |
7.30 P |
第1研修室 |
| D-3 |
算数・数学 |
牧下
英世 |
筑波大学附属駒場中学・高等学校 教諭 |
小・中・高をつなぐ算数・数学教育 |
8.20 A |
ヴェルクホール |
| E-1 |
理科 |
中村理科工業株式会社スタッフ |
科学おもしろ体験III |
7.23 A |
理科室 |
| E-2 |
理科 |
大原
一興 |
横浜国立大学大学院 助教授 |
三浦半島エコミュージアム |
7.24 A |
第2研修室 |
| E-3 |
理科 |
徳山
英一 |
東京大学海洋研究所 教授 |
メタンハイドレート |
8. 4 A |
第2研修室 |
| F-1 |
生活 |
森
里美 |
松戸市立中部小学校 教諭 |
子どもの学びの過程を大切にした学習指導 |
7.24 P |
第1研修室 |
| F-2 |
生活 |
久野
弘幸 |
愛知教育大学 助手 |
指導にいきる評価のあり方 評価規準づくり |
7.31 P |
第1研修室 |
| F-3 |
生活 |
府川
芳子 |
二宮町立二宮小学校 教諭 |
指導にいきる評価のあり方 授業実践をとおして |
8. 1 P |
第1研修室 |
| G-1 |
音楽 |
鈴木
恭介 |
和楽器奏者 |
THE おはやし |
7.22 P |
総合福祉会館 |
| G-2 |
音楽 |
丸山
忠璋 |
横浜国立大学教育人間科学部 教授 |
音楽療法の視点を取り入れた評価 |
8. 5 P |
第1研修室 |
| G-3 |
音楽 |
橋本
龍雄 |
リコーダー奏者 |
リコーダーはもっと楽しくなる |
8.20 P |
第1研修室 |
| H-1 |
図工・美術 |
橋本
敬子 |
横浜市教育委員会指導課 指導主事 |
Aコース<造形の(あそび)模擬授業> |
7.30A/31A |
総合高校 美術室 |
| H-2 |
図工・美術 |
塩谷
良策 |
横須賀総合高等学校 教諭 |
Bコース<テラコッタに挑戦!> |
7.30A/31A |
総合高校 造形室 |
| H-3 |
図工・美術 |
杉本
美子 |
版画作家 |
Cコース<版の表現「シルクスクリーン」> |
7.30A/31A |
総合高校 メディア室 |
| I-1 |
家庭、技術・家庭 |
高田
敦子 |
手芸インストラクター |
リサイクル手織を楽しもう |
7.22 A |
第1研修室 |
| I-2 |
家庭、技術・家庭 |
中林
由美子 |
県教育庁教育部義務教育課 指導主事 |
小・中学校の学びをつなぐ |
8. 6 P |
ヴェルク第1会議室 |
安良岡
靖史 |
| I-3 |
家庭、技術・家庭 |
青島
純夫 |
県教育庁教育部保健体育課 指導主事 |
TTによる食教育の実践 |
8.18 P |
ヴェルク第1会議室 |
| J-1 |
外国語 |
佐野
正之 |
横浜国立大学 名誉教授 |
教師の指導力を伸ばすアクション・リサーチ |
7.25 A |
ヴェルク第1会議室 |
| J-2 |
外国語 |
緑川
日出子 |
昭和女子大学人間文化学部 教授 |
第二言語習得理論に基づいたインタラクティヴな授業展開 |
8. 1 A |
第2研修室 |
| J-3 |
外国語 |
谷口
幸夫 |
都立武蔵村山高等学校 教諭 |
授業のバージョンアップ |
8.18 A |
第2研修室 |
| K-1~3 |
体育、保健体育 |
本市小学校教諭 3人 |
学校水泳指導法講習会 |
7.22-24A |
大塚台小学校プール |
| K-4~8 |
体育、保健体育 |
本市小学校教諭 10人 |
小学校指導法講座 |
7.30-31AP |
鶴久保小/ |
| /8.1P |
横須賀サブアリーナ |
| K-9 |
体育、保健体育 |
島田
信弘 |
横須賀共済病院 整形外科医 |
学校体育におけるスポーツ障害と健康管理 |
8.21 A |
横須賀アリーナ |
| ミーティングルーム |
| K-10 |
体育、保健体育 |
本市中学校教諭 2人 |
中学校実技指導法講座「バレーボール」 |
8.21 P |
横須賀アリーナ |
| (サブアリーナ) |
| L-1 |
道徳 |
渡辺
弥生 |
法政大学文学部 助教授 |
かかわる力を育てる体験型道徳実践 |
7.31 A |
第1研修室 |
| L-2 |
道徳 |
田沼
茂紀 |
高知大学教育学部附属実践総合センター 助教授 |
子どもの視点で進める道徳教育 |
8. 5 A |
第1研修室 |
| L-3 |
道徳 |
野口
芳宏 |
元北海道教育大学教授 教育学者 著作家 |
幸福の条件・担任道徳のススメ |
8.19 A |
総合高校メディア室 |
| M-1 |
特別活動 |
鈴木
栄子 |
横浜市教育委員会 指導主事 |
豊かな人間性を育む特別活動 |
7.25 P |
ヴェルク第1会議室 |
| M-2 |
特別活動 |
渡邊
直美 |
川崎市教育委員会 指導主事 |
個性を生かす特別活動の指導と評価 |
8. 4 P |
第2研修室 |
| M-3 |
特別活動 |
本市小学校教諭 2人 |
ふれあい・学びあい |
8.18 A |
ヴェルク第1会議室 |
| N-1 |
障害児教育 |
植木
きよみ |
神奈川LD協会理事 |
先生に知ってもらいたいこと |
7.28 P |
文化会館中ホール |
| N-2 |
障害児教育 |
廣瀬
由美子 |
国立特殊教育総合研究所 分室 主任研究員 |
気がかりな子に対する指導方法とシステムづくり |
8. 4 A |
第1研修室 |
| N-3 |
障害児教育 |
安藤
正紀 |
県教育庁教育部障害児教育課主幹兼指導主事 |
特別支援教育時代に生きる教師 |
8.19 A |
ヴェルク第1会議室 |
| O-1 |
総合的な学習の時間 |
成田
幸夫 |
大府市立大府北中学校 校長 |
総合的な学習と学校づくり |
7.22 P |
文化会館中ホール |
| O-2 |
総合的な学習の時間 |
加藤
明 |
京都ノートルダム女子大学 教授 |
価値ある総合的な学習を生み出す評価のすすめ |
7.25 A |
第1研修室 |
| O-3 |
総合的な学習の時間 |
上杉
賢士 |
千葉大学 教授 |
プロジェクト学習のノウハウを学ぼう |
7.29 P |
文化会館中ホール |
| P-1 |
幼児教育 |
荻須
洋子 |
芸術教育研究所 おもちゃコンサルタント |
牛乳パックで遊んじゃおう |
7.24 A |
第1研修室 |
| Q-1 |
学校給食 |
小林
一弘 |
保健所生活衛生課食品保健担当 主査 |
調理作業のここを見直そう |
7.28 A |
総合福祉会館 |
| Q-2 |
学校給食 |
黒田
豊
|
パシフィク・メディカル・フィットネスクラブ 健康運動指導士 |
柔らか体で健康な毎日を |
7.28 P |
総合福祉会館 |
| Q-3 |
学校給食 |
臼井
一茂 |
県水産研究所企画経営部 |
魚を知る |
7.29 A |
正庁 |
| Q-4 |
学校給食 |
大居
ゆう子
他2人
|
県商工労働部商業観光流通課主事 他 |
生活習慣病予防とは パートI・II |
7.29 P |
正庁 |
| R-1 |
学校保健 |
小澤
竹俊 |
横浜甦生病院ホスピス病棟長 |
生と死 「いのちの教育」とは |
8. 1 A |
ヴェルクホール |
| R-2 |
学校保健 |
松本
俊彦 |
横浜市立大学医学部附属病院神経科 |
病める若者の現状とケア |
8. 1 P |
ヴェルクホール |
| S-1 |
国際理解教育 |
粕谷
恭子 |
聖マリア小学校英語科 非常勤講師 |
「えいごリアン」を活用した授業づくり |
7.23 A |
ヴェルク第1会議室 |
| S-2 |
国際理解教育 |
平塚
淑江 |
横須賀市日本語指導員 |
外国籍・帰国児童生徒のよりよい支援のために |
7.30 A |
第1研修室 |
| S-3 |
国際理解教育 |
横須賀市国際教育指導助手 |
小学校の先生のための英会話教室 |
8.18 P |
第2研・理科室 |
| ・コンピュータ室 |
| T-1 |
支援教育 |
小林
潤一郎 |
明治学院大学 助教授 |
自閉症の理解と対応 |
8. 6 A |
第1研修室 |
| T-2 |
支援教育 |
加藤
醇子 |
クリニック かとう |
アスペルガー症候群の理解と対応 |
8. 6 P |
第1研修室 |
| U-1 |
教育課題 |
鹿嶋
研之助 |
千葉商科大学 助教授 |
高等学校における総合的な学習の時間 |
7.25 P |
総合高校メディア室 |
| U-2 |
教育課題 |
髙木
展郎 |
横浜国立大学 教授 |
高等学校における評価のあり方 |
8. 1 P |
総合高校メディア室 |
|
(指導主事:木屋・望月・椿本・北村)
▲TOPに戻る
教育情報セクション 
|
7月の教育研究所研修講座
◎初任者研修
23日(水)9:30『児童・生徒指導』
◎11年次研修
25日(金)9:30『教科指導』
28日(月)~8月1日(金)
『社会体験研修』(各事業所)
◎教育課題研修
1日(火)15:30
『学校における生き方指導』
◎教育課程担当者(小)研修
25日(金)13:30
『新しい学校づくりと授業づくり』
◎教育相談研修 (希望研修)
4日(金)15:30
『LD児、ADHD児への支援のあり方』
◎理科研修講座(すべて申し込み制です)
2日(水)15:30
理科基礎技術講座第2回
『理科における評価の工夫』
22日(火) 9:30
科学教養講座第1回
『ロボット工学と未来I』
28日(月)13:30
科学教養講座第2回
『ロボット工学と未来II』
29日(火) 9:00
理科基礎技術講座第3回
『海岸生物の観察法』(走水小)
◎情報教育研修講座
(すべて申し込み制です)
1日(火)16:00 画像処理3
4日(金)16:00 ホームページ作成1
8日(火)16:00 ホームページ作成2
|
以下はすべて9:00開始
23日(水)
一太郎1
24日(木)
一太郎2
25日(金)
ワードA
28日(月)
ワードB
29日(火)
表計算1
30日(水)
表計算2
31日(木)
プレゼンテーション1
|
|
■夏季休業中の研修に関して
情報教育研修についてこれまでもお問い合わせがありましたが、月報や指導の必携に載っている実務コースは、日ごとに異なった内容での研修になります。詳しい内容につきましては、イントラネットの申し込みサイトでご覧下さい。
ネット上での申し込みが可能になり、参加申し込みを前日ぎりぎりまでのばすことは可能ですが、会場その他の関係で調整が必要なため、理科の科学教養講座(7月22日と7月28日)につきましては7月4日を締め切りとさせていただきます。
なお、夏季休業中の情報教育研修講座につきましては、6月20日に第1回の締め切りをさせていただきました。ここまでに申し込まれた方は受講決定とさせていただきます。まだ、若干の余裕がありますので、追加で申込みを受け付けます。イントラネットよりお申し込み下さい。第2回の締め切りは7月10日とします。希望者が定員を超えましたら同一内容の講座をもう一つ設定し、追加申込いただいた中で調整をします。午前になるか、午後になるかはご希望に添えませんが、ご了承下さい。
その他の講座につきましても、昨年から夏季休業中の参加希望が大変多くなっておりますので、場合によっては今後、会場や日程の変更もあり得ます。その際はこちらからの連絡が夏季休業直前になってしまうかも知れませんが、ご承知おき下さい。
■科学教養講座のご案内
鉄腕アトムが生まれた年になりました。ロボットとは何なのか、どこまで鉄腕アトムに近づけたのか、これからのロボットはどのようになっていくのか、開発研究にあたっている先生に最新の話を伺ったり、2日目はお一人ずつ簡単なマイコン制御プログラムをコンピュータで作り、それを組み込んだ自動車を製作します。初心者でもできるレベルですので、どなたでも大丈夫です。
2日目は定員制(20名)になります。滅多にない機会ですのでぜひお申し込みの上、ご参加下さい。

|
指導主事
高木 TEL:837-1338
一栁 TEL:836-2418
坂庭 TEL:836-6104
▲TOPに戻る
こくばん
研究員会だより |
|
教育史資料研究員会
『教科・教科外研究会変遷史』 |
|
教育研究所「教育史資料」研究員会では、昨年度より、横須賀市における戦後の教科・教科外研究会の沿革や活動の変遷をまとめることをテーマに研究を進めてきました。
横須賀市ではこれまでに、教科研究会の活動の変遷をまとめたものとして、『戦後の横須賀教育』という冊子を作成していますが、この冊子には、昭和20年から昭和39年までの記録しか収められていません。
そこで、本研究員会では、各種の資料をたよりに昭和39年以降の研究会の変遷史をまとめることを主な仕事としました。
「戦後の横須賀教育」には、次のような事柄が年表形式で記載されています。
(1) 国や神奈川県が行った教科に関係する主要事項(例えば、全国研究集会・県の研修や本市の学校教育に関係があったと思われる各種教育団体の動向)や改訂された各教科の目標
(2) 本市における各学校の研究活動、教育委員会や教育研究所の主催行事、各年度における特筆すべき研究会の活動
(3) 上記のものの注記及び当時の教育の流れや傾向を筆者の観点から記述したものなど
|
本研究員会の具体的な活動として、昨年度は、小・中学校の教科研究会の会長・副会長名、研究テーマ、研究内容などを一覧表にまとめました。
さらに、各研究会に関する資料の発掘や確認を行いながら、昭和39年以降の「研究会変遷史」を現在まとめているところです。
変遷史作成にあたっては、およそ40年ほど時代をさかのぼることになりますので、中には、研究会の記録が残っていないこともあります。
そうした場合は、「研究所所報」や「教育委員会要覧」などをもとに、確認作業を進めています。研究の成果は、平成16年3月に研究紀要として発行することになっていますので、各学校でご活用いただくよう宜しくお願いします。
『横須賀教育史II』
長塚 直機(夏島小学校)
池野 操(長沢中学校)
桐生すみ子(小原台小学校)
|

-7月22日(火)から夏季研修講座が開校します-
今年は教科に関する講座数が多くなりましたのでふるってご参加下さい。
また「国際理解教育」「支援教育」及び「教育課題」について新たに講座を設けました。
なお、申し込みはすべてオンラインを使用しますので「夏季研修要項」をご覧下さい。
▲TOPに戻る