月報 2002年度 3月号
平成15年(2003年)3月1日
編集発行・横須賀市教育研究所/代表・小山 雄二
横須賀市久里浜6-14-3 / TEL(046)836-2443(代)
(〒239-0831) / FAX(046)836-2445
E-mail: admini@kenkyu.yknet.ed.jp
巻頭
|
完全学校週5日制での
土・日曜日の過ごし方
|
|
各地区にある公民館では、子ども映画会・囲碁体験教室・紙飛行機や風車などの昔遊び教室・子ども焼き物教室・親子凧作り教室・料理教室・工作教室・親子ゆかた着付け教室が行われた。親子歴史巡り・子ども探検隊などでは、人や自然にふれあいながら楽しく学んでいる。図書館では、おはなし会・人形劇・手作り絵本教室・小学生の科学遊びなどが人気だ。自然・人文博物館では、ほぼ毎週市内各地で自然観察会などが行われている。青少年会館や青少年の家では、マジックショー・マンガ教室・キャンプ、水彩画教室・親と子の演劇鑑賞会などが工夫され、また、スポーツ教室では、体力つくり・水泳・卓球・親子スキー・ヨット・登山などが楽しまれている。
◆ 公的な施設・団体だけでなく、自然保護やボランティアなどの活動に積極的に取り組んでいる市民団体が、共同で小・中学生を対象とした土・日体験プログラム「すかっ子セミナー」(自然系A~C、国際理解、福祉、郷土史の計6コース)を企画・実施している。また、観音崎自然博物館では、「海とのふれあい環境体験学習」のテーマで、海ぼたるを見る・海藻標本教室・磯の生物体験・干潟や森の観察などが行われている。
◆ 横須賀市教育委員会では、これらの地域教育の活用のために今年度から、土・日に開かれる学習・体験活動の情報を集めたホームページ「ウィークエンド・ポケット」を開設した。
(http://www.kyoui.yknet.ed.jp/
kyouiku_ka/donichi/index.html)
◆ 学校・家庭・地域が協力し、文化施設・社会施設を活用して、子どもたちにとって意味のある2日間をつくりあげることが重要な課題である。その際、子どもたち自身が2日間の過ごし方を主体的に考えることが何より大切である。
(小山 雄二)
|
|
◆ 平成14年(2002)年4月から、毎週土曜日を休みとする完全学校週5日制が、私立学校を除き国公立全ての幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校及び養護学校ではじまった。完全学校週5日制は、学校、家庭、地域社会が一体となって、子どもたちに『生きる力』を育み、健やかな成長を促すものである。
◆ 完全学校週5日制の実施直前の文部科学省による意識調査では、小学校の場合、休日とする土曜日には、「外で何か活動をしたい」という答えが多く、中・高校生は、「ゆっくり寝る」という回答が多かった。一方、多くの大人は「休日には積極的に子どもの体験活動にかかわりたい」と思っているという回答が多かったそうである。1年が経過したが、実際はどうであったのだろうか。
◆ 文部科学省は、完全学校週5日制への対策として、学校以外の教育機関などにも野外での自然体験、スポーツ、文化体験など学校では味わいにくい活動の機会を設けるよう協力を依頼した。
◆ 平成14年10月22日には「完全学校週5日制の実施に伴う事業の実施・子どもたちの参加状況に関する調査」がまとめられ、公表された。それによると、1学期(4~7月)中の土曜日に自然体験、スポーツなどの体験活動を実施した市区町村は全体の88.7%に上った。地域の体験活動へ参加した小学5年生の割合は57.3%、中学2年生の割合は24.5%だったそうである。
◆ 横須賀市教育委員会では、完全学校週5日制の実施を契機に学校以外の教育機関との連携を一層深めようとしている。
|
|
▲ TOPへ戻る
特集
| 今、学校では ~この1年を振り返って~ |
 |
|
『一人一人』・・・『いい仕事』へ
|
|
新教育課程での一年を終えて
|
|
久里浜小学校 新倉 邦子
|
|
坂本中学校 加藤 直竹
|
|
昨年3月、『何事も全力投球で!』を合言葉に素晴らしい6年生を中学に送り出し、同時に私も前任校を<卒業>しました。
そして4月、11年目の転勤。希望に満ちていた私でしたが、なかなか思うように進まない学級経営・・・。自分の考える理想の2年生像に少しでも近づかせたいと懸命の毎日でした。 そんな時、自宅の近所に住む世界的に著名な心臓外科医S氏を訪問した時の言葉が頭をよぎったのです。「私は、目の前にいらっしゃる患者さん一人ひとりをどうにかしたい、いい仕事をしたいのです。」S氏は、奢ることなく淡々と話されました。『一人ひとり』と『いい仕事』。私は改めてこの二つの言葉を味わい直し、目の前にいる子どもたち『一人ひとり』に今まで以上に寄り添って、全力で対応していこうと心に強く思いました。連日の職員室の皆さんからの温かい励ましの言葉、日毎に増す保護者の方からの支援。これらを頼りに、日々試行錯誤しながら工夫を積み重ねてきた結果、学級経営にもようやく光が見えてきたのです。そして今、毎朝クラスに向かう私の足取りの何と軽やかなこと。子どもたちの笑顔の何と素晴らしいこと。
今、教育界には問題が山積しています。でも何より大切なのは、自分の学級、学年、学校の仕事を確実にすることなのは言うまでもありません。足場をしっかり固めてこそ、問題解決の道が開け、新しい教育課題にも柔軟に対応できると感じています。そして、今後も子どもたち『一人ひとり』の目の輝きを大切に、私の考える『いい仕事』をしていきたいと思います。
さあ今日も、元気に笑顔で教室へ・・・。
|
|
五日制の完全実施に向けて、本校では昨年度より日課の見直しを行い、朝清掃や昼のHRを実施し、授業終了後すぐに部活動や委員会活動に取り組めるように放課後の時間確保に努めてきました。また、行事の精選にも力をいれ、体育祭の規模の縮小やキャンプ・社会見学の廃止などを行いました。
その様な中で迎えた新年度でしたが、とにかく忙しい一年であったように思います。6時間の日の増加による放課後の時間の減少。生徒の活動に利用されていた土曜日の午後が無くなった事。選択教科や総合学習での多種多様な試み。何事も新しい事に取り組む時は大変ですが、慣れないせいもあり、その大変さを実感した一年でした。
その様な中で迎えた新年度でしたが、とにかく忙しい一年であったように思います。6時間の日の増加による放課後の時間の減少。生徒の活動に利用されていた土曜日の午後が無くなった事。選択教科や総合学習での多種多様な試み。何事も新しい事に取り組む時は大変ですが、慣れないせいもあり、その大変さを実感した一年でした。
特に、総合学習に費やす労力の多さを感じます。「体験」と「課題追究」を柱にして取り組んでいますが、学校探検から始まり、地域探検、地域清掃、福祉体験、国際理解、そして各種の講演会等。実施当初ということで欲張りすぎている事もありますが、それぞれの企画、生徒の準備とまとめそして評価と毎日が追われるような日々でした。従来の行事は大幅に削減された割には、今まで以上の多忙さです。
さらに、小学校との連携も課題です。小学校の時とまったく同じ内容の講演会が実施されたり、体験学習の重なり等がありました。
今後、学区自由化の中での多数の小学校からの入学による調整の煩雑さも予想されます。今は、何よりその内容を精選し来年度に備えたいと思います。
|
▲ TOPへ戻る
横須賀教育史
|
【写真に見る横須賀の教育のあゆみ 6】
|
|
6・3制義務教育の成立
アメリカ教育使節団の報告を受けて、新しい日本の教育のあり方が教育基本法・学校教育法として公布されたのは、昭和22(1947)年3月31日で、翌4月1日か、6・3・3・4制の新しい教育制度は慌ただしくスタートした。理想は高く掲げていたが、現実の裏づけを伴わないままのスタートであった。とくに、新しい中等教育として誕生した中学校の場合、校舎と教員の確保から始めることになった。
横須賀の場合、旧軍隊の建物を校舎に転用できたことは、他市にはない好条件であった。
横須賀市長を四期(昭和32年~48年)つとめた長野正義氏は、新制中学発足時、不入斗中の初代校長として、4ヶ月の短い期間ではあるが、開校の準備にあたっている。
同校30周年記念誌(昭和52年)に「生みの苦しみ」と題して原稿を寄せているが、新制中学校が誕生した頃の様子がうかがえて興味深い。
昭和22年(1974)年に「校長日記」として書かれた一部を引用してみよう。
| 4月23日 |
不入斗中学校校長の辞令を受けた。 |
| 4月26日 |
神奈川軍政部マックマナス氏出席して、県下中学校長会議が開かれた。 |
| 4月28日 |
不入斗中学校生徒を各小学校ごとに召集し、開校式の心得を話す。
|
| 5月1日 |
教職員の辞令が交付された。 |
| 5月2日 |
教職員・父兄・生徒全員集まり大掃除を行い、初の職員会議を開き、横須賀市立不入斗中学校の門標を掲げた。 |
| 5月5日 |
午前10開校式挙行。 |
| 5月6日 |
生徒登校し教室の清掃作業をする。 |
| 5月7日 |
授業開始。学習机、椅子や黒板なく、坐したままの授業が当分続く。 |
| 5月30日 |
花崎組より椅子300脚運びこまれ、一脚3人掛けの授業ができた。 |
|
|
| 6月23日 |
後援会理事会は、生徒用机・椅子調達のため、30万円の借かんを議決した。
かくて7月8日から12日の間に、生徒用机400個(2人用)、椅子(一人掛け)800脚が備えつけられ、生徒は、正常な姿勢で学習できるようになった。
開校以来2ヶ月あまり、教職員は不備な条件の中で悪戦苦闘されたが、物的整備は殆ど父兄の熱意によってなされた。 |
いっぽう、入学してくる生徒の様子はどうだったか。昭和34(1959)年の『池上中十年誌』は、つぎのように記している。
この時入学した生徒たちは、身体も小さく体力も落ち、他校と比べても劣っていた。
服装も様々。モンペ姿・ワラ草履・作業帽姿が普通のようで、衛生面もひどく、何日も入浴せず、手足・襟首が垢で真っ黒なもの、白癬などの皮膚病、トラコーマの眼病に冒されているもの・・・。食料の欠乏は昼は家に帰るもの、帰ると見せて昼抜きにしているもの、弁当の菜がタクワンだけで、それを隠して食べている生徒等・・・。 |
「勉強どころではない」時代だったが、子どもたちが学校を休むことはあまりなかった。
|

開校当時の池上中学校校舎
校舎は旧海軍工廠の見習い工員宿舎を転用した。市立豊島家政女学校を本部とし、旧制市立工業学校の一部を借用して発足した。写真は同居の家政女学校生徒である。
|
|
| (教育史・図書資料担当 佐藤隆晃) |
|
▲ TOPへ戻る
研修セクション
|
実践的指導力を高める研修・研究
年度末が近づき、各学校とも年間反省を基に、次年度の計画を立案しているところですが、研修についもこの時期に年間を総括し、次年度の研修プランを企画していくことが求められています。
教員の研修についは、その職責の特殊性にかんがみ、他の一般公務員と比較して特段の配慮が要請されることから、教育公務員特例法において、教員の主体的研修を期待し、その自覚を促したり、任命権者にきめ細かい対応を求めるなど、より積極的な位置付けがなされています。
各自が研修計画を企画する
研修の内容については、平成11年度の教養審の答申において、各教員がライフステージに沿った研修計画をたて、実践していくことを求めています。
次年度新設される11年次研修においては、各人の評価に基づいた研修計画にしたがって、研修が実施されます。新しく制度化された研修ですが、この研修計画の立案は本来はすべての教員に求められるものだと受け取っていくべきではないでしょうか。
そのためには年間反省が実施されるこの時期に、今年の指導を振り返り、次年度の目標や内容を検討し、計画しておくことが必要です。
研修・研究成果の蓄積を
また、今年度の研修・研究の成果は、ネットワーク等を利用して積極的に発信し、共有化することによって多くの教育実践に生かしていくことが必要です。教職員のグループウエア等整備された道具をうまく活用していきたいものです。
|
教育課程担当者研修
レポートの閲覧ができます
今年度、各学校から資料として提供いただきました、「特色ある学校づくり」に向けてのレポートをイントラネット上で閲覧できるようにしました。場所は、教育情報センターのトップページにある「教育課程担当者実践報告」をクリックすると小・中学校の一覧画面になりますので、中から閲覧したい学校名を選択してください。
|
|
|
平成15年度の研修概要について、今年度との変更点は次の通りです。
(1) 新設する研修
・フォローアップ研修
・ALT研修
・学校図書館司書教諭研修
・初任者研修拠点校指導教員研修
・ 国際理解教育研修<夏季研修>
・支援教育研修<夏季研修>
・教育課程(高等学校)研修<夏季研修>
(2) 内容の変更・名称変更の講座
・初任者研修
実施方法が変更されます。
・11年次研修
今年度実施した社会体験研修を基に法制化された研修を実施します。
(3) 研修回数を増加する研修
・夏季研修 各教科領域研修
・理科研修
各研修の内容・回数等については4月に各学校に配布する研修講座案内、6月に配布予定の夏季研修講座案内をご覧下さい。
また、研修の申込については、すべてイントラネット上で行います。講師への質問も事前に把握できるよう、準備中です。
さらに、次年度より教育研究所でエル・ネット(教育情報衛星通信ネットワーク)が導入されます。これにより、文部科学省や独立行政法人教員研修センター等での研修等が受信できるようになります。必要に応じてVTR等へのダビングも行い、各学校で有効に活用していただけるよう準備していきたいと考えています。
|
県立教育センター長期研修員
研 究 発 表 会
平成14年度の県立総合教育センター長期研修員の研究発表会が3月4日(火)、5日(水)に実施されます。横須賀市関係では逸見小学校の野村教諭が4日に『社会科学習における「主体的学び」の追究-地域教材の開発を通して-』というテーマで発表されます。詳細は県立総合教育センターより各校に直接送付されている案内をご覧下さい。
|
|
| |
| |
(研修セクション TEL834-9308 : 中山・木屋・北村)
▲ TOPへ戻る
教育情報セクション
|
○ 年度末に理科室の整備を
3学期も終わりに近づきました。複数の先生で使用する理科室が、日頃の忙しさの中でつい、片付けないままになってはいないでしょうか?
最近、実際に見た理科室を紹介しましょう。
流しの中には雑巾やアルミホイル、薬包紙などが詰まり、窓際には洗っていない試験管と集気びんが埃にまみれています。教卓には塩酸のビンと透明な液体が入ったビーカーが、生徒卓には温度計とマッチ箱がもう何週間も置かれたままです。天井の蛍光灯は2本が切れています。2つのごみ箱は分別できるようにはなってはいません。実験卓には小さな落書きが目立ちます。掲示物ははがれ、カレンダーは昨年のままです。
もちろん、こんな状態が一つの学校で見られたわけではありません。授業の効率や事故防止ばかりでなく、子どもの集中度においても、学習環境を整えることは、とても大切だと思います。
この年度末に、理科室の大掃除を兼ねて、ぜひ先生方の手で整理整頓をお願いします。
|
|
○ 図書の紹介
-評価・評価規準-
| ・小学校国語科 全単元の絶対評価 1~6年 |
| 清水 健 |
明治図書 |
| ・小学校算数科 全単元の絶対評価 1~6年 |
| 小島 宏 |
明治図書 |
| ・小学校社会科 全単元の絶対評価 3~6年 |
| 寺崎 千秋 |
明治図書 |
-指導方法-
| ・ プレゼンテーションの授業技術 |
| 喜岡 淳治 |
明治図書 |
| ・ 小学校 個に応じる少人数指導 |
| 加藤 幸治 |
翠明図書 |
-学校管理・運営-
| ・ 学校の自己点検・自己評価の手引き |
| 小島 宏 |
明治図書 |
| ・ 保護者の要望をどう受けとめるか |
| 小笠原 文孝 |
フレーベル館 |
※ この他、各教科ごとの評価規準・教育相談・教育論についても図書室の新着コーナーに配架してあります。
|
平成14年度 横須賀市教育研究所長期研修講座の受講を終えて
森崎小学校教諭 片田 敦子
「子どもたちの生きる力をはぐくむ情報活用能力の育成をめざして」というテーマのもと、一年間研究をおこなってきました。
昨今、いろいろなメディアにおいて、「教育の情報化」、「情報教育の推進」、「情報活用能力」等の言葉を日常的に目にすることが多くなり、また、各地の学校での情報機器やネットワークを活用した学習や活動の様子もよく話題にあがっています。
横須賀市においても、学校におけるPC室の設置やネットワークへの接続等の環境が整うことで、この1年間、子どもたちが情報機器やネットワークを活用する機会が格段に増えてきました。このような状況の中、さらに小学校における情報教育を推進していくための方法を探ってきました。
具体的な研究活動としては、『学年別情報リテラシー指導計画』、『コンピュータ活用教科単元例』、『情報教育指導用の掲示物や教材』等の作成に取り組みました。子どもたちの発達段階に合わせて、無理なく情報活用能力を育成していけるよう、在籍校での実践授業をおこないながら作成にあたりました。
また、教職員の情報機器操作のスキルをアップしていくことで、情報教育をさらに推進することができ、校務を効率化できると考え、教職員のためのコンテンツ作成にも取り組みました。
様々な操作マニュア等を作成し、イントラネット上での公開を通して、広く利用していただきました。
自身の研修としては、市内外の研修会等に参加したり、学校ITアドバイザー会議への出席を通して、いろいろな地域や学校での情報教育の推進状況を知ることができ、大変参考になりました。
一年間という期間ではありましたが、大きな視野に立ち、社会や学校が求めている「教育の情報化」について多くのことを学ぶことができました。
今後、学校現場に戻り、今年度の研究を生かし、子どもたちが学ぶ意欲を持てる、楽しい学習を実現していきたいと思います。
(教育情報セクション
小谷直通TEL837-1338・坂庭直通TEL836-6104・一栁直通TEL836-2418)
▲ TOPへ戻る
こくばん
|
 研究委員会だより 研究委員会だより
小学校・英語活動研究員会
Let's Enjoy English !
|
「国際海の手文化都市」である横須賀市において、「小学校における英語活動のあり方」を追究していくため、今年度に発足した研究員会です。英語活動を学習指導要領総則(「総合的な学習の時間」部分)に例示された「国際活動の理解」の一環として、ごのように展開していくのか、また、今年度から横須賀市の全小学校に配置された「国際教育指導助手」(ALT)とどのように連携していくか、といった課題を中心に研究を進めています。
昨年7月には、鴨居小学校3年生において、本研究員会主催の研究授業を行いました。子どもたちが自然に、そして、楽しんで活動する姿を通して、私たちの目指す英語の一例を示すことができたと自負しています。研究協議では、
(1) 歌やスキット・チャンツなどを取り入れた楽しい雰囲気作り
(2) ALTとの連携の重要性
(3) カリキュラム作りと積み重ねの大切さ
(4) 教材・教具の有効な活用例
|
|
などが話し合われました。
また、11月には、夏島小学校の研究会において、6年生の外国活動を公開しました。ここでは、「楽しむ・親しむ」段階を経て、知的欲求をもとに「自ら学ぶ」段階の活動を提案しました。(これら二枚の資料は、各学校に送付済みですので、ぜひご覧ください。)
私たちは、英語活動の理念・方法・内容・評価として、次のことを確認してきました。
*英語に親しませ、好きにさせる。(理念)
*遊び感覚を生かす。(方法)
*子どものニーズを生かす。(内容)
*子どもの喜ぶ姿を助長する。(評価)
今後は、これらの理念をさらに具体化した「カリキュラム作り」・「授業作り」・「ALTとの連携」に関するモデルプラン及びアイデア集を作成していきたいと考えています。
稲永 純子 (鴨居小学校)
岩田 嘉純 (夏島小学校)
武石 太一郎 (汐入小学校)
|
|
|
今年度も研究所月報の原稿を、たくさんの先生方にお願い致しました。厚くお礼申し上げます。
各学校で新しい教育課程がスタートし、大変お忙しい中、限られた字数で〆切までに原稿をまとめていただき、本当にありがとうございました。少しずつでしたが、先生方の貴重な実践や考えを紹介することができました。
来年度も月報の充実を図っていきたいと思いますので宣しくお願いいたします。
<お詫びと訂正>
2月号1ページの右段下から5行目「他動」は「多動」の誤りでした。
ここにお詫びと訂正をさせていただきます。
申し訳ありませんでした。
|
▲ TOPへ戻る









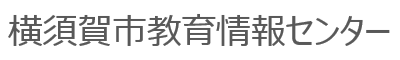


 研究委員会だより
研究委員会だより