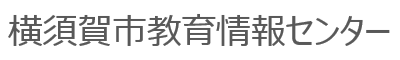カテゴリ:3.横須賀市のうつりかわり
3.横須賀市のうつりかわり
| 1.かわってきた横須賀駅 |
| 2.かわってきた横須賀市 |
| 3.道路や鉄道のうつりかわり |
| 4.土地の使われ方と人口のうつりかわり |
| 5.公共しせつのうつりかわり |
| 6.これからの横須賀市 |
1.かわってきた横須賀駅
わたしたちが生まれる前の横須賀市は、どのような様子だったのでしょうか。昔の写真や昔の人の話から気づいたことを話し合いましょう。

2.かわってきた横須賀市
|
|
左の地図から分かるように、横須賀市は、約90年前ごろから、衣笠村や田浦町など、周りの町や村といっしょになって、どんどん大きくなっていきました。 また、下の写真は、60年から50年ほど前と今の横須賀市の様子です。 |

3.道路や鉄道のうつりかわり

日本は、外国とのつきあいを始めてから、陸軍や海軍の力を強くするために、横須賀にも、いろいろな軍のしせつをつくり始めました。
そして、海軍の大切なしせつが横須賀にうつされると、軍の人や物を運ぶために、鉄道が必 要になりました。そのため、1889(明治22)年に横須賀線が開通し、横浜や東京との交通が、とても便利になりました。
始めのころは、単線で、蒸気機関車が客車を引っぱって、1日6おうふくしていました。また1930(昭和5)年、浦賀から横浜の黄金町まで、湘南電車 (今の京浜急行)が走るようになりました。

戦争がはげしくなった1944(昭和19)年、久里浜の海軍しせつ へ、国鉄横須賀線がのばされ、また、この2年前の1942(昭和17)年に、京浜急行久里浜線がしかれました。


4.土地の使われ方と人口のうつりかわり
横須賀市の人口がふえつづけていたので、平成町など、うめたてによって新しいまちもつくられました。うめたてられた土地には、住宅の他に、大型スーパーなどの商業しせつや公園や大学がつくられました。
これらのしせつは、現在も多くの人々に利用されています。少しずつ発展してきた横須賀市ですが、現在、いくつかの課題があります。その一つは、人口がへり続けているということです。43万人以上いた人口も、少しずつへり続け、平成30年には40※万人より少なくなってしまいました。また、子どもや働く世代の大人が減り、お年寄りが増えていることも、これか ら先のことを考えると、課題となります。そのため、これまで以上に、子どもからお年寄りまで、みんながくらしやすいまちづくりをすすめていくことが必要なのです。
また、横須賀市にはいろいろな国から来た人やその家族も、たくさん住んでいます。様々な文化にふれあえることは大切なことですが、一方で、様々な文化や歴史を持った人々が、ともにくらしやすいまちづくりをすすめていくことも課題となっています。

※ 令和5年2月現在、横須賀市の人口は378,241人です。
5.公共しせつのうつりかわり
戦争が終わり、軍によって使われていた場所は、 多くの公共しせつに生まれ変わりました。軍の倉庫が多く立ちならぶ場所は、「くりはま花の国」に変わりました。また、「ウェルシティ」や「横須賀芸術劇場」がある場所も、もとは軍のしせつがあった場所です。他にも、公共しせつだけでなく、研究所や工場があつまる場所に生まれ変わった所もあります。

(1)学校のうつりかわり
横須賀市では、今から100 年以上前の明治時代に学校ができ始めました。横須賀市に住む人々の数が増えるにつれ、しだいに学校の数も増えてきました。これまで、横須賀市の学校に 通う児童の数が一番多かったのは、1981(昭和56)年で、45281人です。その後、児童の数は少しずつ減ってきています。そのため、新しい学校もできていますが、なくなってしまったり、いっしょになったりする学校もあります。
ア 横須賀にはじめて学校ができたころの様子(およそ120年前)

イ 戦争のころの学校の様子(およそ80年前)

ウ 戦争が終わってからの学校の様子(およそ70年前)

エ 昭和後期の学校の様子(およそ50年前)

(2)横須賀製鉄所
ア 横須賀製鉄所ができたころ
「横須賀製鉄所(※1)」ができるまでの横須賀は、人や荷物が集まる港町でした。多くの人々は、 となり村などへ行くときは山の尾根道などを歩きました。遠くに行くときには、船に乗りまし た。そんな港町の横須賀村に、「横須賀製鉄所」とよばれる、船をつくる工場ができました。

「横須賀製鉄所」ができたことにより、たくさんの人が工場のまわりに住むようになり、横須賀がさかえていきました。横須賀村は、1876(明治9)年、横須賀町になりました。さらに、下町(※4)の海岸がうめたてられ、新しいまちがつくられていきました。

※1 横須賀製鉄所は、1871(明治4)年には、「造船所」とよばれるようになり、明治のなかごろになると「海軍工廠(かいぐんこうしょう) 」と名前が変わりました。
※2 それまで、日本では尺貫法という長さの測り方を使っていました。1尺=およそ30cm
※3 フランス人のヴェルニーは、船をつくる工場だけでなく、1869(明治2)年、観音崎に、日本で初めて西洋式の灯台をつくりました。また、「横須賀製鉄所」に必要な水は、走水から水道(土管をうめたもの)をつくってひきました。
※4 下町と呼ばれる所は、小川町、若松町、米が浜 、日ノ出町、安浦町とつづく海岸ぞいの町で、うめ立てによってつくられました。
イ 横須賀製鉄所でつくられた「横須賀丸」
「横須賀製鉄所」では、まず大小2せきの蒸気船がつくられました。大きい方には、後に「横須賀丸」という名前がつけられました。この船の走る曜日や、船が出る時刻は、きちんと決められていました。この工場では、今もわたしたちが使っている西洋式の時間や曜日を、早くから使っていたのです。 また、同じころの1871(明治4)年に郵便(※5)が始まるなど、西洋の仕組みがたくさん取り入れられてきました。

※5 日本の郵便制度の祖と言われる前島 密の墓が芦名の浄楽寺にあります。
6.これからの横須賀市
わたしたちが住む横須賀市は、様々な歴史をへて、少しずつ発展しながら、現在のすがたになっています。横須賀市は、2030年に向けて「変化を力に進むまち。横須賀市」を未来像に掲げ、次のようなまちを目指しています。
・すべてのひとが自分らしく輝けるまち
・人も自然も共生するまち
・「やりがい」と「やりたい」からしごとが生み出されるまち
・「自分ごと」の意識が未来の環境を守るまち
激しい時代の変化の中でも、「誰も一人にさせない」という変わらぬ精神を大切に、変化を力に未来に向けて進んでいきます。
| 猿島公園 |  |
|
猿島は東京湾でたった一つの自然島です。島には、そのままの自然や歴史的なものが、残されています。この大切な財産をいかして「島まるごと博物館」として整備びし、公園にしました。2016(平成28)年、日本いさんに登録。 |
|
| 海と緑の10,000メートルプロムナード(うみかぜの路) |  |
|
JR横須賀駅から観音崎までの海ぞいの約10kmを、海と緑にふれながら、楽しく歩くことができる遊歩道です。1984(昭和59)年から整備が進められ、2001(平成13)年に「うみかぜの路」と愛称を決定し、横須賀の象徴的な道を目指しています。 |
|
| 横須賀美術館 |  |
|
海が見わたせる県立観音崎公園走水園地内に、美術鑑賞や学習活動ができる美術館が、2007(平成19) 年にオープンしました。 |
|
| 浦賀レンガドッグの活用 |  |
|
1899(明治32)年に建造されて 2003(平成15)年に閉鎖されるまで、1,000隻以上の船の製造や修理を行ってきた歴史のある貴重な施設です。 |
|
| 長井海の手公園 (ソレイユの丘) |  |
|
市民の交流とまわりの海や農地をいかした「いこいの場」として、 2005(平成17)年につくられました。ふれあい動物村、大型遊具、アスレチック、キャンプ場などをそなえています。 |
|
| 横須賀リサーチパークの推進 |  |
|
長沢・野比地区の丘陵地に、情報通信をはじめとする研究開発しせつが、1997 (平成9)年につくられました。世界的てきな 研究開発拠点をめざしています。 |
|
| 湘南国際村 |  |
|
横須賀市と葉山町にまたがる地区に、国際交流を目的とするしせつづくりが進められています。1994(平成6)年にオープンしました。 |
公開日:2023年10月16日 08:00:00
更新日:2025年03月31日 12:51:57