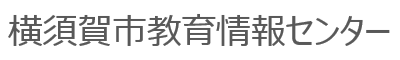-
カテゴリ: はじめに
横須賀のまち -

横須賀市については、小学校3,4年生が中心となって学習します。
横須賀市の自然や施設、農業、漁業、工業、商業などを学習し、今まで以上に横須賀市について深く知ってもらうために作成しました。
いろいろなことを調べるときにぜひ活用してください。
内容のお問い合わせは、教育研究所へ
(外部リンク:横須賀市のサイトに移動します)
公開日:2023年10月16日 12:00:00
更新日:2025年02月17日 12:57:27
-
カテゴリ:1.わたしたちの市の様子調べ
1.わたしたちの市の様子調べ -
1.横須賀市の地図をひろげて 2.市の土地の広がりや高さ 3.土地の使われ方 4.交通の様子 5.みんなのための市のしせつ 6.古くから残るたて物
1.横須賀市の地図をひろげて
横須賀市を空から写した写真です。あなたの住んでいるまちをさがしてみましょう。
横須賀市は三浦半島のまんなかにあり、東は東京湾、西は相模湾にはさまれています。
わたしたちの住んでいる横須賀市は、どのような特ちょうをもった市なのでしょうか。
資料を使ったり、実際に見学したりして、横須賀市の様子を調べてみましょう。

谷戸 
小山にかこまれたひくい土地を谷戸といいます。谷戸には、せまくて急な坂が多く、階だんになっている道もあります。平地の少ない横須賀市では、そのような土地も、昔から工夫しながら使われています。 うめ立て地 
昔、海だったところをうめ立てて土地にしています。うめ立てられてできた土地は、商業施設、工場、住宅など、様々な目的に使われています。 農地 
農業がさかんな地域は、主に、市の南部と西部に集まっています。地域によって、作られている作物にもちがいがあります。 港 
海にかこまれた横須賀には、いくつもの港があります。漁業のための港、工業製品やその材料を運ぶための港、観光客を運ぶための港、アメリカ軍や自衛隊の港など、港によって役わりがちがいます。
2.市の土地の広がりや高さ
下の地図は、土地の高さによって色分けした地図です。
※黄色(高い)↔ 青色(低い)
横須賀市は平地が少なく、低い山が海の近くまでせまっていることがわかります。
横須賀市には海や山があり、海にかこまれた島もあるなど、自然が作り出した美しい場所がいくつもあります。市内の真ん中から南東に向かって、平作川が流れています(川の両岸は、コンクリートでほそうされています)。
猿島 観音崎 平作川 


荒崎 立石 大楠山 


コラム ~もっと知りたい谷戸のこと~ 山が多い横須賀市では、せまい土地を有効に使う工夫がされてきました。
その工夫の一つが、谷戸に立ちならぶ住宅です。谷戸とは、小山にかこまれた低い土地のことです。せまい谷戸にも住宅がたくさんたっているのは、横須賀市の特ちょうの一つです。また、谷戸のまち同士をむすび、生活を便利にするために、トンネルもたくさん作られました。そういう理由もあり、横須賀市は全国の中でも、とてもトンネルの多いまちになっています。谷戸のまち トンネル 

3.土地の使われ方

(1)東京湾側の様子(北~東)
追浜地区には、自動車をつくる工場をはじめとして、自動車関係の部品をつくる工場が多く集まっています。また、船をつくる工場もあります。
久里浜地区の平作川のまわりも工場が集まっています。
工場が集まる追浜 
JR横須賀駅や京急線汐入駅のまわりには、横須賀芸術劇場などの文化施設や、大きなショッピングセンターがあります。横須賀中央駅近くの小川町には、市役所、郵便局、消防署など、わたしたちのくらしに大切なたて物ものがたくさんあります。
東京湾側には、うめ立てによってできたまちがいくつもあります。平成町は平成4年にうめ立てがかんせいしました。工場、マンション、大学、大きなお店などがたてられ、わたしたちの生活が便利になりました。
また、東京湾側には、たくさんの港(長浦港・横須賀本港・横須賀新港・浦賀港・久里浜港など)があります。これらの港を合わせて、「横須賀港」とよんでいます。東京湾側の港の多くは、ものを運ぶために使われています。横須賀芸術劇場 市役所 横須賀中央の商店街 


平成町のうめ立て地 横須賀本港 アメリカ海軍横須賀基地の門 


(2)東京湾側から相模湾側の様子(南~西)
光の丘にあるYRP(横須賀リサーチパーク)は、スマートフォンやコンピュータなどの情報産業にかんけいのあるたて物があります。
また、葉山町ととなり合わせた地域には、湘南国際村があります。ここには、外国の人との交流を目的としたたて物や、様々な研究施設が集まっていて、日本全国や外国から人々が会議や研修のためにおとずれます。山をひらき、たくさんの家がたてられたところもあります。横浜横須賀道路の開通によって、横須賀インターチェンジや衣笠インターチェンジのまわりにも、家がたくさんたてられました。森崎にあった市立横須賀高等学校の場所も住宅地にかわりました。
YRP(横須賀リサーチパーク) 湘南国際村 池上の住宅地 


北下浦地区や西地区には、横須賀市の畑のほとんどが集まっています。キャベツがもっとも多くつくられ、かぼちゃ、だいこん、すいかなどもつくられています。また、観光農園があり、みかんやいちごなど、季節のくだものを観光客が収穫できるようにもなっています。
西地区(長井)の畑 畑での収穫の様子 観光農園(いちご狩り) 


相模湾側の港の多くは、漁港として使われています。長井地区や大楠地区の港には、イワシをはじめ多くの魚が水あげされています。また、わかめやこんぶを育てたり、たこやいかをとったりする漁港や、つりを楽しむ人のためにつり船を出す港もあります。
佐島漁港 船上で干されるイカ 加工される魚 


4.交通の様子

わたしたちは、自分たちの住んでいるまちから他のまちや市へ行くときに、自動車や鉄道(電車)を使います。
市内には、横浜横須賀道路や国道・県道・市道が通っています。横浜横須賀道路は、本町山中線・三浦縦貫道ともつながっています。国道では、16号線と134号線が他の市やまちにつながっています。
また、鉄道はJR横須賀線と京急線が通っています。それらは、市内や他の町との行き来に役立っています。
横須賀の港からは、様々な国や国内各地に船が出ています。久里浜港からは、となりの千葉県とをむすぶフェリーが出ています。●道路の様子
馬堀海岸までのびた横浜横須賀道路 市外へ通じる国道16号線 

●鉄道
京急線 JR横須賀線 

横須賀中央駅 横須賀駅 

●海の交通
フェリーのりば 
5.みんなのための市のしせつ
市には、いろいろな公共しせつがあります。公共しせつは、地域に住すむわたしたちが、よりよく生活できるように作られたしせつです。どのようなしせつが、どのようなはたらきをしているのでしょうか。

(1)市役所のはたらき
小川町に、横須賀市役所があります。人々が安心してかいてきにくらすために、市役所では、様々な相談や手続きをすることができます。
また、税金を使って、様々な仕事が進められています。たとえば、公園や、山や川などの自然環境の管理をしたり、ゴミの回収をすすめたり、 水道のせつびを整えたりしています。
さらに、これからの横須賀市がよりよく発展していくよう、未来に向けての計画なども話し合われています。
このように、市役所は横須賀市を住みよいまちにするための、中心的な役わりをはたしているしせつなのです。市役所のたて物 市役所1階の様子 

(2)健康生活をささえるウェルシティ
逸見には、ウェルシティというたて物があります。 これは、横須賀市の人たちが、生きがいをもって、いきいきとすごせるようにつくられました。
ウェルシティには、健診センターや生涯学習センター、すこやかんなど、様々なしせつがあります。このように、様々なしせつが一つに集まることで、多くの人が目的にあわせて利用できるようになっています。ウェルシティのたて物 すこやかんのプール 

図書室の様子 大学集室の様子 

6.古くから残るたて物
まちに残る古いたて物には、いくつか種類があります。

大津諏訪神社は、天長元年(824年)にたてられました。毎年御柱(おんばしら)祭が行われます。横須賀市には、お寺や神社など、古くから残る建物がたくさんあります。
信楽寺は、阿弥陀如来という仏様をまつっています。江戸時代の終わりに活やくした、坂本龍馬という人のおくさんで、おりょうさんのおはかがあります。
公開日:2023年10月16日 10:00:00
更新日:2025年03月31日 12:04:34
-
カテゴリ:2.市の人々の仕事
2.市の人びとの仕事 -
わたしたちの横須賀市には、住宅や工場の多いところ、田や畑の多いところ、役所や商店の多いところなどがあり、場所によってちがいがみられます。
わたしたちのまちではどのような仕事をしている人がいて、生活とどのようにつながっているのでしょうか。
1.仕事調べ 2.田や畑で働く人 3.海で働く人 4.工場で働く人 5.商店で働く人
1.仕事調べ

農家の仕事 海の仕事 工場の仕事 


商店の仕事 建設の仕事 人や物を運ぶ仕事 


公務員の仕事(市役所や学校) サービスの仕事(理髪店など) 


2.田や畑で働く人
(1)農業のさかんなところ




夏のかぼちゃや冬のだいこん、キャベツはよく知られていますが、その他にも季節や土地のようすにあわせて作物を作っています。
観光農地ではみかんやいちご作りにも力を入れています。観光農地には、多くの人がおとずれ、みかんがりやいちごかり、いもほりを楽しんでいます。
(2)農家の仕事について
農家の藤平さんのお話
農家の仕事は、自然相手の仕事なので、日々いろいろなことを考えながら仕事をしています。天候、品種、時期、肥料、畑(土壌)など、毎年野菜を作っていますが、うまく作れない年もあります。そのため、地域のネットワークも大切で、品種や肥料のことなど情報交換が大切です。
きれいな形の野菜が作れるように、いつも研究しています。

(3)農家の工夫
農家の人たちは、作物がよくできるようにどのような工夫をしているのでしょう。
早春キャベツと春キャベツ 
キャベツを2回に分けてうえ、収かくする時期をずらします。 フェロモントラップ 
害虫が好きなにおいを入れて、害虫を集めてたいじします。 農薬をまく回数を少なくする ことができます。 シーダーテープ 
大根を均等に素早く種まきができるように、すでにテープの中に種が均等に入っています。
少人数でも種まきができます。
寒冷紗(かんれいしゃ) 
水分の蒸発をおさえ、防寒の役割があります。特に種まきの後に使用され、鳥や害虫から作物を守るためにも利用されています。 ガラス温室 ビニルトンネル 

作物が育ちやすい温度にします。 トラクター 新しい機械の展示会 

機械を使って畑をたがやしたり、種をまいたりして、少ない人数で早く仕事ができるようにしています。また、新しい機械を買うために、展示会にも出かけます。 洗浄機と選別機 
大根を洗い、大きさ別にわける機械です。少ない人数で正確に選別し、早く仕事をすることができます。 農業ノート 
毎年育てる野菜の品種や時期、天気などはノートに残しておきます。
仕事の時の天気も大切ですが、事前の天気も畑の状態に関係するので大事です。
(4)出荷の様子
主な出荷先

最近では、地元でとれた野菜を地元の人が食べられるように、農場や農家から、直接スーパーマーケットなどにとどけられたり、出荷された野菜が直売場で売られたりしています。
どこでだれが作った野菜なのかが、分かる仕組みも工夫されています。そのため、わたしたちは、安心して新せんな野菜を買うことができるのです。
箱の中には農家の人が大事に育ててくれた野菜が入っています。大事にトラックに乗せていきます。 
できるだけすきまがないように並べていきます。 
主に関東近郊に出荷されます。
3.海で働く人
わたしたちの横須賀市は、海に囲まれているので、漁業の仕事をしている人もいます。
(1)市内の漁家(ぎょか)
東京湾側と相模湾側の漁家をくらべて、 どこにどのくらい集あつまっているのでしょうか。

長井漁港 走水漁港 

(2)水あげされる魚
漁が終わると、港にはたくさんの魚が水あげされます。横須賀ではどのような種類の魚がどのようにして、水あげされるのでしょうか。

漁が終わると、船は港にもどってきます。 
水あげの準備をします。 
とってきた魚を漁師さんが網にいれます。 
機械を使って水あげをします。 
ふだんとれる魚の他に、カジキマグロやジンベイザメ、サメなど、めずらしい魚や大きい魚が、とれるときもあります。 
(3)養殖の仕事
漁師の人たちは、魚をとるだけでなく、魚や貝、海そうをそだてる仕事もしており、それを養殖業といいます。とくに、横須賀ではワカメなどを育てています。

ロープについた小さいワカメを4~ 5cm に切って、太い親網にはさみます。つめすぎないで、広く間かくをとったほうが栄養がとどいて大きく育ちます。
次に、うきとおもりをつけて、ロープをはりつけます。はる場所は抽選できめます。

ワカメは海のミネラルと太陽の光で育つので、潮の流れが良い場所ほど育ちます。1月の終わりごろ180cmくらいの大きさになったら、とって天日干しにします。
(4)海で働く人の思い
漁師の嘉山さんのお話
朝が早く時間が不規則なので、慣れるまでが大変です。魚をとったり、船からおろしたりと、力仕事が多いので、足腰が大切になってきます。また、天気が悪い日や南風が吹く日は、海が荒れてとても船がゆれて危険です。夏の暑さ、冬の寒さ、潮の速さなど自然条件に左右される毎日で、きびしく感じることもあります。
その反面、季節を直に感じたり、魚がたくさんとれたりしたときはとてもうれしく、やりがいを感じます。大変な労働の中だからこそ、チームが一体となり、みなさんにおいしい魚を届けたいと思っています。長井漁港の漁師さんのお話
最近は、若い漁師がへってきています。大変なことも多いけれど、とてもやりがいのある仕事です。変化していく海や自然環境にうまく対応して、若い世代に引き継いでいくために、働きやすい環境づくりに努めています。
みなさんも子どものうちに海の楽しさを知って漁師になる子が増えるとうれしいです。

(5)魚が家に届くまで
漁師の人たちは、海に出てしごとをしています。えものによって、時期(じき)や仕事の時間がちがうようです。

機械と人の手で、魚をしゅるいや大きさごとに分けます。
小さい魚や、形がくずれている魚はせんべつされます。
種類ごとに分けられたら、魚市場に出荷し、入札や競りが行われます。 
入札された魚は各地に運ばれます。魚の値だんは、毎日かわります。
水あげされた魚は、料亭や、豊洲市場、各スーパーなどに運ばれて行きます。また、保冷車を使うと、新鮮な魚が生のままで24時間ももつので、遠くまで運ばれるようになりました。
そのほかにも漁師さんが、水あげした魚を自分たちで加工して各地のスーパーで販売しています。


4.工場で働く人
(1)横須賀にある工場
わたしたちの周りには、工場でつくられたものがたくさんあります。

(写真1・2)追浜工業団地…大きな船や自動車をつくる工場のほか、自動車に使われるブレーキなどの部品や、家具をつくる工場など50以上の工場があります。
(写真3)田浦地区…放射線や電球、蛍光灯・水銀灯をつくる工場などがあります。
(写真4)久里浜テクノパーク…この地区には、プロジェクターや音楽用CD、DVD などをつくる工場があるほか、製品の研究や開発をすすめる工場もあります。
・久里浜工業団地…金属機械をつくる工場が100 ほどあります。
・久里浜港…食品をつくる工場などがあります。
・平成町地区…ビルの中にあるのが特徴で、ゲーム機をつくる工場などがあります。
(2)工場と交通

(3)横須賀にある工場の数

(4)工場で作られている物
横須賀市の工場では、くらしに欠かせないものを作っています。その中でも輸送機が半数を占めています。

・輸送機(自動車や船、航空機)
・電機(冷蔵庫や洗濯機、テレビなど の家電製品のほか、照明器具、携帯 電話、通信機器など)
・機械(油圧ショベルなどの建設機械 や農業用トラクター)
・食品(牛乳やチーズなどの乳製品や 製菓、製糖、食肉加工)(5)工場で働く人の思い
こんにゃく工場の森さんのお話
夏は工場内がこんにゃくの湯気と熱気で暑く、冬は寒く、季節のえいきょうを受けやすいのでとても大たいへん変です。また、朝早くからこんにゃくをつ
くったり、重いこんにゃくを運んだりと大変なこともありますが、「今まで食べられなかったこんにゃくが食べられるようになった。」など、お客さんの声がとてもうれしく、やりがいになっています。
今後もおいしいこんにゃくをとどけられるように、工夫や努力を続けていきたいと思います。★こんにゃく工場の工夫

作業をするときは、ほこりやかみの毛が入らないように白衣を着たり、ぼうしをかぶったりして、作業をしています。
また、仕事をする前に、手をきれいにあらったり消毒などもしたりしています。
【穴あきこんにゃく】
さしみこんにゃくのたれがこぼれにくくなり、おいしく食べられる工夫です。また、おでんの味がしみやすく、よりおいしく食べられるように工夫しています。
【季節の商品】
夏にはところてんやそうめん風こんにゃくなどの冷やして食べるとおいしい商品を主につくっています。冬にはおでんやおなべに使えるこんにゃくなど、お客さんが季節ごとに必要な商品をつくるように工夫しています。
【こんにゃくを使ったデザートづくり】
若い人にも、食べてもらえるようなこんにゃくを使ったデザートをつくっています。カロリーが低くておなかがいっぱいになるのでオススメです。
5.商店ではたらく人
(1)買い物をするところ
わたしたちは、どのようなところで買い物をしているのでしょうか。

買い物は、いろいろなところですることがわかりました。最近では、家からインターネットを利用して買い物をしたり、宅配を利用したりする人がふえています。
(2)横須賀で買い物ができるところ

(3)地域の商店調べ
わたしたちは、生活に必要な物を、スーパーマーケットや商店街やコンビニエンスストアなど、様々な商店で買います。また、最近は、商店に行かずに、家にとどけてもらう宅配や、インターネットで買い物をすることもできます。
それぞれの商店には、どのような特ちょうがあるのでしょうか。ア スーパーマーケットの店づくり
スーパーマーケットには、広い駐車場があります。店内も広く、商品の種類もとても多いの が特ちょうです。
広い駐車場 たくさんの種類の品物 

手書きのポップ 広告の商品 地元の商品 



スーパーマーケットでは、店がある地いきの特ちょうや、店を利用する人の願いを考え、たくさんの人に利用してもらえるよう、工夫や努力をして、店づくりに取り組んでいます。
イ 商店街の店づくり
商店街では、それぞれの地いきに古くからある店がたくさんあります。お店を開いている人も、多くはその地いきにくらしている人です。それぞれの商店街には、それぞれの取り組みや工夫があります。
お店の人と相談して買い物 大売り出し 


ウ コンビニエンスストアの店づくり
コンビニエンスストアは店の数が多く、夜おそくても開いています。そのため、いつでもど
こでも気軽に買い物をすることができます。いつでも買える コンビニエンスストアのサービス 

銀行サービスなどが利用できるATM キャンペーンのお知らせ 


地いきの商店ではたらく人は、それぞれの特ちょうを生かした店づくりをしています。どの商店でも、地いきにくらす人や買い物をする人の願いにこたえることができるような工夫や努力をしています。そのため、買い物をするわたしたちも、ほしい商品や利用したいサービスにあった商店をえらぶことができます。
公開日:2023年10月16日 09:00:00
更新日:2025年03月31日 12:11:27
-
カテゴリ:3.横須賀市のうつりかわり
3.横須賀市のうつりかわり -
1.かわってきた横須賀駅 2.かわってきた横須賀市 3.道路や鉄道のうつりかわり 4.土地の使われ方と人口のうつりかわり 5.公共しせつのうつりかわり 6.これからの横須賀市
1.かわってきた横須賀駅
わたしたちが生まれる前の横須賀市は、どのような様子だったのでしょうか。昔の写真や昔の人の話から気づいたことを話し合いましょう。

2.かわってきた横須賀市

左の地図から分かるように、横須賀市は、約90年前ごろから、衣笠村や田浦町など、周りの町や村といっしょになって、どんどん大きくなっていきました。
また、下の写真は、60年から50年ほど前と今の横須賀市の様子です。

3.道路や鉄道のうつりかわり

日本は、外国とのつきあいを始めてから、陸軍や海軍の力を強くするために、横須賀にも、いろいろな軍のしせつをつくり始めました。
そして、海軍の大切なしせつが横須賀にうつされると、軍の人や物を運ぶために、鉄道が必 要になりました。そのため、1889(明治22)年に横須賀線が開通し、横浜や東京との交通が、とても便利になりました。
始めのころは、単線で、蒸気機関車が客車を引っぱって、1日6おうふくしていました。また1930(昭和5)年、浦賀から横浜の黄金町まで、湘南電車 (今の京浜急行)が走るようになりました。

戦争がはげしくなった1944(昭和19)年、久里浜の海軍しせつ へ、国鉄横須賀線がのばされ、また、この2年前の1942(昭和17)年に、京浜急行久里浜線がしかれました。


4.土地の使われ方と人口のうつりかわり
横須賀市の人口がふえつづけていたので、平成町など、うめたてによって新しいまちもつくられました。うめたてられた土地には、住宅の他に、大型スーパーなどの商業しせつや公園や大学がつくられました。
これらのしせつは、現在も多くの人々に利用されています。少しずつ発展してきた横須賀市ですが、現在、いくつかの課題があります。その一つは、人口がへり続けているということです。43万人以上いた人口も、少しずつへり続け、平成30年には40※万人より少なくなってしまいました。また、子どもや働く世代の大人が減り、お年寄りが増えていることも、これか ら先のことを考えると、課題となります。そのため、これまで以上に、子どもからお年寄りまで、みんながくらしやすいまちづくりをすすめていくことが必要なのです。
また、横須賀市にはいろいろな国から来た人やその家族も、たくさん住んでいます。様々な文化にふれあえることは大切なことですが、一方で、様々な文化や歴史を持った人々が、ともにくらしやすいまちづくりをすすめていくことも課題となっています。

※ 令和5年2月現在、横須賀市の人口は378,241人です。
5.公共しせつのうつりかわり
戦争が終わり、軍によって使われていた場所は、 多くの公共しせつに生まれ変わりました。軍の倉庫が多く立ちならぶ場所は、「くりはま花の国」に変わりました。また、「ウェルシティ」や「横須賀芸術劇場」がある場所も、もとは軍のしせつがあった場所です。他にも、公共しせつだけでなく、研究所や工場があつまる場所に生まれ変わった所もあります。

(1)学校のうつりかわり
横須賀市では、今から100 年以上前の明治時代に学校ができ始めました。横須賀市に住む人々の数が増えるにつれ、しだいに学校の数も増えてきました。これまで、横須賀市の学校に 通う児童の数が一番多かったのは、1981(昭和56)年で、45281人です。その後、児童の数は少しずつ減ってきています。そのため、新しい学校もできていますが、なくなってしまったり、いっしょになったりする学校もあります。
ア 横須賀にはじめて学校ができたころの様子(およそ120年前)

イ 戦争のころの学校の様子(およそ80年前)

ウ 戦争が終わってからの学校の様子(およそ70年前)

エ 昭和後期の学校の様子(およそ50年前)

(2)横須賀製鉄所
ア 横須賀製鉄所ができたころ
「横須賀製鉄所(※1)」ができるまでの横須賀は、人や荷物が集まる港町でした。多くの人々は、 となり村などへ行くときは山の尾根道などを歩きました。遠くに行くときには、船に乗りまし た。そんな港町の横須賀村に、「横須賀製鉄所」とよばれる、船をつくる工場ができました。

「横須賀製鉄所」ができたことにより、たくさんの人が工場のまわりに住むようになり、横須賀がさかえていきました。横須賀村は、1876(明治9)年、横須賀町になりました。さらに、下町(※4)の海岸がうめたてられ、新しいまちがつくられていきました。

※1 横須賀製鉄所は、1871(明治4)年には、「造船所」とよばれるようになり、明治のなかごろになると「海軍工廠(かいぐんこうしょう) 」と名前が変わりました。
※2 それまで、日本では尺貫法という長さの測り方を使っていました。1尺=およそ30cm
※3 フランス人のヴェルニーは、船をつくる工場だけでなく、1869(明治2)年、観音崎に、日本で初めて西洋式の灯台をつくりました。また、「横須賀製鉄所」に必要な水は、走水から水道(土管をうめたもの)をつくってひきました。
※4 下町と呼ばれる所は、小川町、若松町、米が浜 、日ノ出町、安浦町とつづく海岸ぞいの町で、うめ立てによってつくられました。
イ 横須賀製鉄所でつくられた「横須賀丸」
「横須賀製鉄所」では、まず大小2せきの蒸気船がつくられました。大きい方には、後に「横須賀丸」という名前がつけられました。この船の走る曜日や、船が出る時刻は、きちんと決められていました。この工場では、今もわたしたちが使っている西洋式の時間や曜日を、早くから使っていたのです。 また、同じころの1871(明治4)年に郵便(※5)が始まるなど、西洋の仕組みがたくさん取り入れられてきました。

※5 日本の郵便制度の祖と言われる前島 密の墓が芦名の浄楽寺にあります。
6.これからの横須賀市
わたしたちが住む横須賀市は、様々な歴史をへて、少しずつ発展しながら、現在のすがたになっています。横須賀市は、2030年に向けて「変化を力に進むまち。横須賀市」を未来像に掲げ、次のようなまちを目指しています。
・すべてのひとが自分らしく輝けるまち
・人も自然も共生するまち
・「やりがい」と「やりたい」からしごとが生み出されるまち
・「自分ごと」の意識が未来の環境を守るまち
激しい時代の変化の中でも、「誰も一人にさせない」という変わらぬ精神を大切に、変化を力に未来に向けて進んでいきます。
猿島公園 
猿島は東京湾でたった一つの自然島です。島には、そのままの自然や歴史的なものが、残されています。この大切な財産をいかして「島まるごと博物館」として整備びし、公園にしました。2016(平成28)年、日本いさんに登録。
海と緑の10,000メートルプロムナード(うみかぜの路) 
JR横須賀駅から観音崎までの海ぞいの約10kmを、海と緑にふれながら、楽しく歩くことができる遊歩道です。1984(昭和59)年から整備が進められ、2001(平成13)年に「うみかぜの路」と愛称を決定し、横須賀の象徴的な道を目指しています。
横須賀美術館 
海が見わたせる県立観音崎公園走水園地内に、美術鑑賞や学習活動ができる美術館が、2007(平成19) 年にオープンしました。
浦賀レンガドッグの活用 
1899(明治32)年に建造されて 2003(平成15)年に閉鎖されるまで、1,000隻以上の船の製造や修理を行ってきた歴史のある貴重な施設です。
長井海の手公園 (ソレイユの丘) 
市民の交流とまわりの海や農地をいかした「いこいの場」として、 2005(平成17)年につくられました。ふれあい動物村、大型遊具、アスレチック、キャンプ場などをそなえています。
横須賀リサーチパークの推進 
長沢・野比地区の丘陵地に、情報通信をはじめとする研究開発しせつが、1997 (平成9)年につくられました。世界的てきな 研究開発拠点をめざしています。
湘南国際村 
横須賀市と葉山町にまたがる地区に、国際交流を目的とするしせつづくりが進められています。1994(平成6)年にオープンしました。
公開日:2023年10月16日 08:00:00
更新日:2025年03月31日 12:51:57
-
カテゴリ:4.すみよいくらし
4.すみよいくらし -
1.くらしと水道(上水道) 2.くらしと水道(下水道) 3.くらしとごみ
1.くらしと水道(上水道)
(1)水はどこから
わたしたちの毎日の生活では、水道の蛇口をひねると、いつでもかんたんに水を飲むことができます。また、お風呂や洗たくなどにも、水道の水をたくさん使います。生活に欠かせない水道の水は、どこからくるのでしょうか。横須賀市内には、走水にわき水がありますが、水源となる、大きな川や湖はありません。そこで、横須賀市では、相模川や酒匂川など、5 つの系統から水を引いています。



5つの系統というのは、相模川を水源とする有馬系統と小雀系統、その支流の中津川を水源とする※宮ヶ瀬系統、神奈川県の西の酒匂川を水源とする酒匂川系統、横須賀市内に水源のある走水系統です。これらの水源を合わせると、1 日あたり、350,300㎥の水を横須賀市に送おくることができます。これは、小学校のプール、約1,200杯分の量になります。
※以前は、半原水源地や逸見浄水場などからなる半原系統がありましたが、平成27年3月に廃止され ました。ただし、逸見浄水場内にある逸見総合管理センターは、横須賀市内に安全な水をとどけるため、今でも24 時間いつもはたらいています。
(2)きれいで安全な水を家庭へ
水源から送られてきた水は、そのまま飲むことはできません。どのようにして、きれいで安全な水になるのでしょうか。

ろ過のしくみ 活性炭吸着のしくみ 

水源から送られてきた水は、浄水場という所でゴミなどを取り、砂などを使ってろ過かします。そうしてきれいになった水を安全のために殺菌し、飲める水にしています。
このようにしてきれいで安全になった水は、浄水場から、横須賀市内に17か所あるポンプ所に送られ、27か所ある配水池を通って、みなさんの家庭や、学校や病院いんなどにとどけられます。

配水管 大矢部ポンプ場 武山配水池 


2.くらしと水道(下水道)
(1)下水がきれいになるまで
お風呂や洗たく、トイレなど、わたしたちの毎日の生活で使われた後のよごれた水や、降った雨をあわせて「下水」とよびます。

家などで使われた水は、最初に道路の下にうまっている下水道管に入り、途中18か所のポンプ場を通って、浄化センターに集められます。地いきごとに4つの浄化センター(追浜、上町、下町、西)で、水をきれいにして、横須賀市の東側は東京湾に、西側は相模湾に流しています。
降った雨は、下水道管から直接川や海に流れます。
下水道管 ポンプ場内 下水浄化センター 


わたしたちの家や工場などからでた下水は、下水道管を通り、浄化センターにたどりつきます。たどりついた下水は、最初に大きなごみや砂が取りのぞかれます。その後、バクテリアがよごれを食べてしずみます。
最後に、上ずみ水を消毒してから海にもどします。このように、下水はいくつものしせつを通って、少しずつきれいな水にされ、自然の中にもどされるのです。きれいになっていく水

海にもどされた水は、やがて蒸発し、雨となって森や林にたくわえられます。
その水が川の流れとなり、浄水場のはたらきによりふたたび水道水となります。
このように、わたしたちが生活のなかで使う水はじゅんかん※しているのです。※じゅんかん・・・ひとめぐりして、元へもどることをくり返すこと
(2)下水道の役割
下水道には、水をきれいにし、川や海の水質をきれいで、衛生にたもつことの他、様々な役割があります。そのひとつが、大雨がふったときに、まちを浸水から守ることです。下水道に雨水などが、流れ込み、まちに水があふれだすのをふせぐのです。
安心安全なくらしのためにも、下水道の役割は、欠かせないものになっています。また、浄化センターできれいになった水は、様々な場面で再利用されています。市内にある何か所かのトンボの王国では、下水処理をしてきれいになった水を再利用した池や小川があります。そこは、様々な植物や水辺の生き物を見ることができるなど、市民のいこいの場になっています。
台風で平作川の水があふれた舟倉(1974年7月) 下町トンボの王国 

3.くらしとごみ
わたしたちは、くらしの中で毎日たくさんのごみを出しています。横須賀市全体では、どれくらいのごみが出されているのでしょうか。また、わたしたちが出したごみは、どこに運ばれていくのでしょうか。(1)横須賀市のごみの量
右のグラフは、平成10年から平成30年までに、横須賀市で出されたごみの量を表したグラフです。現在行われているごみの4分別収集と、集団資源回収が始まった平成13 年は、前の年とくらべるとごみの量が大きくへり、その後の20年間でも、少しずつへってきているのが分かります。4分別収集や集団資源回収には、どのようなねらいがあるのでしょうか。 
(2)くらしから出るごみと資源物
市町村によって、ごみの分け方や出し方はちがいます。横須賀市では、平成13年度から、4 分別収集と集団資源回収が開始されました。それらは、それぞれ、決まった日に計画的に集められています。
また、令和2年度からは、ごみの分け方が一部変わりました。これは、横須賀市のごみ処理しせつが新しくなったことと関係します。分別のしかたがどのように変わったのか、たしか
めてみましょう。(3)横須賀市で収集するごみ
・4分別収集するごみ
1.燃せるごみ 
(生ごみ・落ち葉・バケツやおもちゃなどのプラス
チック製品・ゴム類・リサイクルできない紙など)2.缶・びん・ペットボトル 
(ペットボトル・缶づめやジュースの缶・金属の
ふた・ジャムや薬くすりのビンなど)3.容器包装プラスチック 
(食品トレイ・おかしの袋・マヨネーズの容器など、プラスチックでできているもの) 4.不燃ごみ (お茶わん、うえ木ばちなどのとうじ器、ガラス) ・その他のごみ
家具やふとんなどは有料で収集、小型家電は無料で回収しています。
(4)地域で集団回収する資源物
1.リサイクルできる紙 
(新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パックなど) 2.古着・古布 
3.缶以外の金属 
(やかん、フライパン、自転車などの金属) 4.蛍光管・電球 (5)ごみのゆくえ
集められたごみは、どこへ運ばれ、どのようになるのでしょうか。横須賀市に住むみなさんが出しているごみは、横須賀市と三浦市とで、協力して処理を行っています。しせつごとに見ていきましょう。
ア 横須賀ごみ処理しせつ「エコミル」
長坂にあるエコミルには、横須賀市と三浦市からごみが集まってきています。このしせつには、「燃せるこみ」や「不燃ごみ」、「そ大ごみ」が運ばれてきています。まず「燃せるごみ」は、下の図のように処理されています。
燃やしたあとに残る灰は、とかして道路をつくる材料などにします。また、燃やしたときに出る熱を使って発電もしています。
「不燃ごみ」や「そ大ごみ」はエコミルに運ばれ、ここで細かくくだいたあと、さらに分別されます。リサイクルできる金属類、燃せるもの、うめ立てるものの3つに分けられます。


令和2年から運転を始めたエコミルの技術のおかげで、これまで「不燃ごみ」だったプラスチック製品やゴム類も「燃せるごみ」として処理できるようになりました。
イ リサイクルプラザ「アイクル」
追浜にあるアイクルには、「缶かん・ビン・ペットボトル」と「容器包装プラスチック」が運ばれます。

アイクルでは、集められたものをリサイクルする会社に引きわたすため、種類ごとに分けて、サイコロのような形にしています。それぞれが、どのような物に生まれ変わっているので
しょう。手作業で分別します サイコロのような形にかためられます 

ウ 最終処分場
「不燃ごみ」や「そ大ごみ」はエコミルで処理されたあと、どうしてもリサイクルできないものとして、三浦市にある最終処分場にうめ立てられることになります。
(6)集められた資源物
段ボール、紙パックなどのリサイクルできる紙類は、アイクルで処理した後、リサイクルする会社に引きわたし、古ぎ、古ぬの類や缶以外の金属はリサイクルされます。
ところで、横須賀市では、どのくらいのごみと資源物が出されているのでしょうか。下のグラフは、横須賀市で出されたごみと資源物の種類別の量を表しています。

次のグラフを見てみましょう。わたしたちのまちではみなさんの協力のおかげで、ほかのまちとくらべても、資源化率が高いことが分かります。

今、世界では「3R」が大切にされています。「3R」とは、「リデュース」「リユース」「リサイクル」のことです。※
アイクルでも、「3R」をよびかけています。横須賀市は、集団資源回収がとてもさかんです。回収率は全国トップレベルです。これは、「3R」を進めることに、つながっています。
毎月決められた日に行われる集団資源回収は、町内会や子ども会が計画し、回収業者が家庭から出る資源物を回収します。回収業者はリサイクル会社にそれを引きわたします。市役所も、その活動をサポートしています。
このように、家庭・地域・市役所などがそれぞれ協力し合って、資源物の回収をすすめています。※ リデュース・・・(ごみを)へらすこと リユース・・・くりかえし使うこと
リサイクル・・・材料やエネルギーとして有効に使うこと(7)ごみをへらす工夫
集あつめられたごみやしげんぶつは、リサイクルするなどの工夫がされていました。なぜそのような工夫が必要なのか、市役所の人に教えてもらいました。

公開日:2023年10月16日 07:00:00
更新日:2025年03月31日 12:55:21
-
カテゴリ:5.安全なくらし
5.安全なくらし -
1.火事からくらしを守る 2.事故や事件からくらしを守る
1.火事からくらしを守る
(1)火事が起きたら
次のグラフは、横須賀市で起こった火事の件数や、主な火事の原因などをあらわしています。


火事は、自分が気をつけていても、起きてしまうことがあります。
火事が起きたときや火事を防ぐために、だれがどのような働きをしているのでしょうか。また、どのような備えをしているのでしょうか。
(2)様々な人々の働き
火事の知らせ(119番)は、市内のどこから電話をかけても横須賀市の消防指令センターにつながります。ここは、市役所のとなりにあります。
119 番の電話をうけると、すぐに現場に1番近い消防署の消防車と救急車に出動の指令を出します。同時に、警察署や消防団、ガス会社などにも連絡をします。火事のえいきょうが広がらないように様々な関係機関と連けいしています。

横須賀市・葉山町消防指令センター 市内の消防署と出張所 中央消防署 


(3)消防署の仕事
消防署には、様々な役割を持った人々が働いています。現場の状況にあわせて、それぞれが出動していきます。指令がないときにも、日ごろから備えていることがあるようです。


ポンプ車と消防隊 救急車と救急隊 

救助工作車と救助隊 はしご車と救助隊 消防士さんの話
『消防』と聞いて、はじめにイメージするのは「火事」だと思います。でも、火を消すだけではなくて、交通事故で車に閉じ込められた人を助けたり、海にもぐっておぼれた人を助けたりと色々なところで助けをもとめている人を「救助」します。さらに助けるだけ
ではなく、災害が起こらないように「予防」もしています。全て
に共通して言えることは、消防の仕事は人の命や財産を守ること
につながっているということです。(4)まちに見られる消防しせつ
(ア)地域にある消防しせつ
わたしたちのまちで火事がおきたら、すぐに火を消すことができるように、いろいろな努力がされています。たとえば、それぞれの地域には、消火栓や防火水そうなどの消防しせつが、使いやすいように置かれています。

(イ)学校にある消防しせつ
学校には、火やけむりが出たらすぐわかるように、ろうかや教室に熱やけむりの感知機がついています。また、火をすぐに消すための消火器やホース、火やけむりが広がらないようにするための防火とびら(シャッター)などの設備も整っています。

○まちの消防団
みなさんは、消防団を知っていますか。消防団の人たちは、私たちの生活の安全を守るために、いろいろな活動をしています。


消防団訓練 消防団防火教室 音楽隊 


消防団の方の話
消防団は、自分たちが住むまちで火事が起こった時に消防署の方と協力して消火作業を行います。ふだんは、別の仕事をしているので、訓練は仕事が終わった夜8時ごろから行います。仕事でつかれているのでつらく、大変なこともあります。また、24時間いつでも消防局から連絡がくるので、夜中に起こされることもあります。
しかし、地域の中でつながりをもつこと、協力できる地域にするためにわたしたちが中心になって活動していることに、やりがいがあります。
今、消防団員の数は、だんだん減ってきていることが残念です。「自分のまちは自分で守まもる」という気持ちでこれからも活動を続けていきます。(5)救助活動について
救急活動について、わたしたちにできることはなんでしょうか。
次の資料を見て、気づいたことを話し合ってみましょう。


2.事故や事件からくらしを守る
(1)事故が起きたら
次のグラフは、横須賀市で起こった事故の件数などをあらわしています。

事故や事件が起きたときやそれらを防ぐために、だれがどのような働きをしているのでしょうか。また、どのような備えをしているのでしょうか。
(2)110番のしくみ

(3)警察官の仕事
わたしたちの生活の安全を守るために、警察の方々はいろいろな仕事をしています。またどんな時間でもかけつけたり見守ったりできるように、交代で仕事をしています。当番になると、24 時間以上働くこともあります。非番とは、24 時間以上働いたあと、という意味です。



(4)地域を見守っている交番
わたしたちは、落とし物をひろったり、困ったことがあったりすると、交番に相談に行くことがあります。地域の中で困っている人を助ける警察官がいることで、わたしたちは安心してすごすことができています。では、交番の警察官のどんな働きによって、地域の安全が守られているのでしょうか。
警察官は、ずっと交番で待機しているわけではありません。交番の中での仕事のほかに、地域のパトロールをしたり、交通整理をしたりするのも仕事です。また、直接家を訪問して、地域の方のお話を聞くのも大切な仕事です。
交番の仕事も交代で行うことで朝、昼、夜と休みなく続けられています。このようないろいろな仕事を通して、交番の警察官は、地域の様子にくわしくなり、わたしたちの地域の安全を見守ってくれているのです。(5)地域で安全なまちづくりを
地域の安全を守るために、地域の人々による取り組みも行われています。自分たちのまちの安全のために、自分たちで話し合い、工夫していったものやことがたくさんあります。まちに住むみんながととのえていったしせつや活動を調べたり探したりしてみましょう。


町内会館では、自分たちのまちの安全についても話し合っています。 警察による防犯ざだん会が開かれています。 

夕方は週1回、夜は月に数回、まちをパトロールしています。 毎日みんなの登下校を見守っていて、「見守り隊」とよばれています。 

町内会費で、防犯カメラをつけました。
公園や車の多い交差点につけました。町内会は、防災にもしっかりと目を向けています。 

登下校を見守ってくれているのは、PTA の校外委員さんです。 「こども110ばんのお店」や「こども110ばんの車」もあります。 
左のかんばんに注目してみてください。子どもたちの安全のために、地域の人々が警察におねがいをし、数年前から交通ルールがかわりました。
1件でも事故が起きないようにするために、地域の人やわたしたち自身にできることは、まだまだたくさんありそうです。
公開日:2023年10月16日 06:00:00
更新日:2025年03月28日 18:49:12
-
カテゴリ:6.自然災害からくらしを守る
6.自然災害からくらしを守る -
1.昔の大きな災害 2.防災の取り組み 3.学校での取り組み 1.昔の大きな災害

関東大震災時の横須賀中央駅近くの様子
1923年(大正12年)9月1日、「関東大震災」とよばれる大地震が起きました。私たちの市でも家がたおれたり、火事になったりして、大勢の死者が出てしまい、町の大部分が被害を受けました。


上の年表の青い丸(●)は、大雨や暴風によって大きな被害がでた風水害(※)の回数を表しています。赤い丸(●)は、震度5以上の地震による災害です。これを見ると、各時代でいくつかの自然災害が起こっていることがわかります。2011 年(平成23 年)3 月の東日本大震災では、神奈川県でも、大きな被害が出ました。
※風やこう水などによる災害のことを、風水害といいます。


横須賀市の平作川ぞいで、1974年7月7日の七夕水害で避難する人々


2011年3月11日の東日本大震災の後、 ガソリンを入れるためにならぶ車
地震のえいきょうで、食料がとどき
にくくなった、お店の様子
2.防災の取り組み
災害へのそなえは、火事だけでなく、地震や大雨や台風、津波、土砂くずれなどに対しても必要とされています。災害へそなえることを防災といいます。防災の取り組みには、各家庭によって行う「自助」、消防や警察など、国・県・市などが行う「公助」、地いきの人びとが行う「共助」、があります。
(1)家庭でのそなえ(自助)
各家庭で行う「自助」には、家具などがたおれないようにしておくことや、非常時のために、生活に必要な物を用意しておくことなどがあります。
災害が起きたとき、すぐに持ってひなんするための物を「非常用持ち出し品」といいます。また、ひなんした後、家に取りに行けるようにしておく物を「非常用備蓄品」といいます。

新型コロナウィルス感染症の流行をきっかけに、「非常用持ち出し品」や「非常用備蓄品」に、マスク・消毒液・モバイルバッテリー・体温計などをふくめることがすすめられるようになりました。 また、非常食を定期的に食べて、新しいものに入れかえる、ローリングストックに取り組むなど、防災バッグの中身のチェックも必要です。このように、各家庭でも災害に対する意識を高め、さまざまなそなえをしておくことが大切です。
また、災害が起きたとき、どのように行動するのかを、家族で話し合っておくことも大切です。そうすることで、災害が起きたとき、被害を少なくすることができます。(2)横須賀市の防災の取り組み(公助)

市や県、国の防災への取り組みのことを「公助」といいます。
上の図は、関東大震災と同じような地震が起きた時の予想震度です。横須賀市では、災害が起きたときに安全にひなんするために、市内の地いきごとにハザードマップを作っています。ハザードマップには、災害時に危険な場所や、ひなん所がある場所などの情報がのっています。
その他にも、災害にそなえ、さまざまな取り組みをしています。
津波・洪水・土砂くずれなどによる被害が起こりそうな場所や、そこからのひなんのしかたを知らせるため、ハザードマップを作っています。 
市内約400カ所のスピーカーで、「防災よこすか」の放送をしています。 
SNS でも情報を伝えています。 
災害の種類に合わせて、避難場所の設置をしています。 また、災害にそなえ、救助のための訓練をしたり、災害のこわさを伝えたり体験したりするための総合防災訓練を行ったりしています。


救助の訓練の様子 体験コーナーの様子 (3)地いきの人びとの協力(共助)
地いきでの防災の取り組みを「共助」といいます。それぞれの町内では、防災会議を開き、地いきの防災について話し合っています。また、災害時に必要なものを防災収納庫に保管したり、防災訓練を行ったりしています。さらに、各家庭に防災グッズをそろえることをよびかけるなど、各家庭の自助の意識を高める活動も行っています。

防災倉庫には、災害が起きた時に、住民に必要な物が入っています。 
訓練では、じっさいに発電機などをそうさし、使うことができるかどうかの確認もします。 
市・地いき住民、学校などが協力して、ひなん訓練を行っています。 
訓練では、市のしょく員と地いきの人がいっしょに、ひなん所をつくる練習もします。 このように、防災の取り組みは「自助」・「公助」・「共助」があります。それぞれの取り組みは、おたがいに協力し合っています。
また、災害が起きたとき、の被害を減らすことを「減災」といいます。「自助」・「公助」・「共助」の取り組みそれぞれを高め、協力し合い、「減災」を目指すことが大切です。
3.学校での取り組み
学校でも、災害にそなえ、さまざまな取り組みがされています。ひなん訓練もそのひとつです。また、災害が起きた時、地域の人が学校にひなんしてくることがあります。その時のために、必要な物がそなえられていたり、ひなん所のルールが定められていたりします。

さまざまな種類の災害が起きたことを考えて、ひなん訓練をしています。 
小学校にも、水や食料、毛布など、災害時に必要な物がそなえてあります。 
小学校には、小学生が使うための物とひなんして来た地域の人が使うための物が別々に用意されています。 公開日:2023年10月16日 05:00:00
更新日:2025年03月31日 13:24:04
-
カテゴリ:7.くらしを高めるねがい
7.くらしを高めるねがい -
1.地域に残る伝統・文化 2.新しく田畑をひらく 1.地域に残る伝統・文化
(1)横須賀市にある古くから残るもの
横須賀市にも、それぞれの地域に昔から伝わる祭や伝統芸能があります。
○ 市内にある古くから残るものには、どのような願いがこめられ、どのように受けつがれてきたのでしょうか。 
(2)伝統芸能を守り伝えていくために
横須賀市では、一年おきに「民俗芸能大会」が開催されています。市が中心となり、昔から伝えられている伝統芸能をみんなで協力して守るために、また、そうした伝統芸能を残すことで横須賀市の文化を多くの人に知ってもらうために開かれています。
それぞれの地域には、伝統芸能を伝えていくために、いくつかの保存会※があります。その伝統芸能にくわしい人たちが集まって、地域の行事で発表したり、紹介をしたりする活動をしています。静岡県の伊豆から横須賀市の野比に伝えられたとされる「とらおどり」は、保存会の人たちが中心になって、2年に一度発表されています。
太田和の獅子舞 野比のとらおどり 

※ 保存会…文化・伝統芸能・風習などを伝えるために集まった団体。
◎ 市内にある古くから残るものを守っていくために、わたしたちができることは何でしょうか。話し合ってみましょう。
2.新しく田畑をひらく

上の絵は、1907(明治40)年ごろの久里浜(夫婦橋付近)の様子をかいたものです。
この夫婦橋のたもとには、古い石ひが建た っています。この石ひは、今から350 年近く前の1667 年にたてられたもので、およそ、次のようなことが書かれています。「今まで入江※やあれ地だった所を、新しく田や畑につくりかえることができました。しかし、これまでは毎年のように水門や堤防がこわれ、何年も苦労してきました。今後はみんなが幸せになれるよう、神様やほとけ様にお守りいただけるよう、おいのりします。
砂村新左衛門(すなむらしんざえもん)」
※海が陸地にはいりこんだ所。
今の夫婦橋のようす
夫婦橋のたもとにある供養塔


この石ひにきざまれてある砂村新左衛門とは、どのような人なのでしょうか。そして、なぜ苦労して、入江やあれ地だったところを田や畑に作りかえたのでしょうか。また、なぜ多くの村人がそれに協力したのでしょうか。―― これらのぎもんについて調べ、考えてみましょう。
○ 砂村新左衛門は、どのようにして内川新田をつくったのでしょうか。 (1)新田(しんでん)ができる前の久里浜付近のようす
江戸時代※1に書かれた本によると、今の久里浜付近一帯は、平作川※2、佐原川、吉井川が流れこむ大きな入江で、そこは、葦などの草木がおいしげる、自然のままのぬま地がつづいていました。
入江は、潮がひく時刻になると、遠く久里浜海岸の方まで砂浜が顔を出し、所どころに、ぬま地や潮だまり(池のようなもの)ができ、潮があがってくると、浅い海になって、今の久里浜海岸につながってしまいました。
この入江の周まわりには、久里浜・八幡、佐原、久比里、吉井 、久村などの村があり、人び
とは、農業や漁業を行って生活をしていました。
今から350 年以上も前のこの時代は、武士が政治を行う世の中でした。村の人びとは、たくさんの米を年貢※3として、大名※4や将軍※5におさめていました。江戸時代は平和が続き、人口が急げきに増えたため、食べ物の不足が大きな問題になっていました。そこで、新たな田畑の開発が必要だったのです。このような開発によってできた新しい田畑を「新田」といいますが、「内川新田」はそのような新田でできた新しい村の名前なのです。


__________________________________
※1.徳川氏が江戸(今の東京)で政治を行っていた時代。1603 年から1867 年までをそうよびます。※2.大楠山のふもとから流れ出し、久里浜港へとそそぐ、三浦半島の中で一番長い川です。
※3.今の金のことで、農家の人々は、主に米をおさめていました。
※4.将軍から、一万石以上の領地をあたえられていた武士のことです。
※5.日本全国の武士を家来にしていた“武士のかしら”です。
(2)工事がはじまるまで
砂村新左衛門は、吉田新田※1の開発にたずさわりながら、さらに三浦半島へ足を進すすめました。
そして、平作川など、3つの川が流れこむ内川入江を見て、吉田新田での経験を生かして、田や畑につくりかえようと思いたったのです。
新左衛門は、まず、将軍のゆるしをえて、近くの村の人びとに自分の考えを話しました。村の人びとはその話を聞いて、工事に協力することを約束してくれました。
こうして、1660(万治3)年※2、砂村新左衛門を中心に、久里浜付近の村の人々によって、内川入江の工事が始まったのです。

_________________________________________
※1.今の横浜市伊勢佐木町の一帯にありました。
この新田は、そこで商人をしていた“吉田勘兵衛”を中心に開発されたので、そうよばれました。※2. 1659(万治2)年という説もあるようですが、ここでは、横須賀市史の年表の年をのせました。
(3)新田づくり
砂村新左衛門は、まず、吉井の山の下に家を建て、そこに住みました。江戸からうでのたつ職人を何人もよび集め、近くの村からは、自分たちの田や畑をふやそうと、多くの人々がやって来ました。 
工事は、まず、海岸にそって、長い堤防をつくり、波が入江に入らないようにしました。
次に、平作川など、3つの川の両側に土手をつくって、いくつにもみだれて流れていた川を、それぞれ1本にまとめました。そして、周りの土地には水路をつくり、土地をかわかしていきました。そして、近くの山から運んで来た土で、田や畑をつくっていきました。今のように進んだ機械などなかった時代なので、これらの作業は全て人や馬、牛の力で工事は進められました。

また、今の夫婦橋があるところまで、高さ1.8m もある長い堤防が作られ、その間には、長さ約10.8m の2つの水門がつくられました。水門は、潮の満ち引きによって、自然に掛け戸が開閉する仕組みになっていました。しかし、台風や津波で大水が出たときなどは、すぐにこわれてしまったり、堤防ごと
流されてしまったりしたこともあったようです。このように、新田づくりは、自然とのたた
かいもあり、簡単に終わりというわけにはい
きませんでした。しかし、砂村新左衛門と村
の人々は、自然のい力にも負けず、長い時間をかけて内川新田を守っていったのです。

内川新田からは、最初360石の米がとれましたが、開発が進められ、のちに585石の米がとれるようになりました。

砂村新左衛門について 江戸時代に書かれた本によると、この人は、福井県鯖江市の出身の人で、わかいころから各地をまわり、土木工事や農業などの勉強をしていたそうです。
久里浜の正業寺にお墓があります。
↑正方形の台にみぞがあって、水がたたえてあります。

「夫婦橋の人柱(ひとばしら)」の伝説 内川新田をつくるためにかけた橋も、川が大水になるたびに流されてしまいました。こんな事が何回もつづくと、村の人々の中には、「これは、神様がおいかりであるにちがいない。神のいかりをしずめるためには、人柱(ひとばしら)をたてなければ・・・。」という話が出はじめました。
その話はだんだんと広まり、村でも、とくにまずしい家の、美しい娘に、その矢がむけられたのです。「気の毒ではあるが、まずしい家のことだから、お金で何とかなるだろう……。と、村長たちが娘の家に出かけ、「神のためじゃ。村のためじゃ、ぜひ……。」と両親にお金を出してたのみました。
両親はもちろん、娘もこの話を聞いて、たいそう悲しみましたが、まずしい家のこと、「神のため、村のためなら……。」と、しょうちしました。
「人柱(ひとばしら)に娘がたてば、きっと神様はいかりをしずめ、願いを聞いてくれるにちがいない。」と、よろこんだ村人たちは、さっそく用意をはじめました。
まず、大きな箱をつくり、その中に娘を入れると、箱の中に食べ物と鈴を入れ、ふたをしめて橋げたの下に、その箱をうめました。
それからというもの、村人たちが橋のそばを気にしながら通ると、鈴の音が聞こえてきます。しかし、三日たち、四日たちしていくと、とぎれとぎれで、しだいに小さな音になり、しまいには、とうとう耳をすましても聞こえなくなってしまいました。
村人たちは、鈴の音とともに、娘が天にむかえられたと涙ぐみました。
それからと言うもの、橋の工事もどんどんすすみ、夫婦橋(めおとばし)は、どんなに大雨がふりつづいても、流されることはなくなったと言う事です。(田辺悟著「三浦半島の伝説」より)
公開日:2023年10月16日 04:00:00
更新日:2025年03月31日 13:25:27