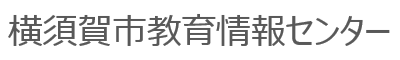カテゴリ:6.自然災害からくらしを守る
6.自然災害からくらしを守る
| 1.昔の大きな災害 |
| 2.防災の取り組み |
| 3.学校での取り組み |
1.昔の大きな災害

関東大震災時の横須賀中央駅近くの様子
|
1923年(大正12年)9月1日、「関東大震災」とよばれる大地震が起きました。私たちの市でも家がたおれたり、火事になったりして、大勢の死者が出てしまい、町の大部分が被害を受けました。 |
 |

上の年表の青い丸(●)は、大雨や暴風によって大きな被害がでた風水害(※)の回数を表しています。赤い丸(●)は、震度5以上の地震による災害です。これを見ると、各時代でいくつかの自然災害が起こっていることがわかります。2011 年(平成23 年)3 月の東日本大震災では、神奈川県でも、大きな被害が出ました。
※風やこう水などによる災害のことを、風水害といいます。
 |
 |
|
横須賀市の平作川ぞいで、1974年7月7日の七夕水害で避難する人々 |
|
 |
 |
|
2011年3月11日の東日本大震災の後、 ガソリンを入れるためにならぶ車 |
地震のえいきょうで、食料がとどき |
2.防災の取り組み
災害へのそなえは、火事だけでなく、地震や大雨や台風、津波、土砂くずれなどに対しても必要とされています。災害へそなえることを防災といいます。防災の取り組みには、各家庭によって行う「自助」、消防や警察など、国・県・市などが行う「公助」、地いきの人びとが行う「共助」、があります。
(1)家庭でのそなえ(自助)
各家庭で行う「自助」には、家具などがたおれないようにしておくことや、非常時のために、生活に必要な物を用意しておくことなどがあります。
災害が起きたとき、すぐに持ってひなんするための物を「非常用持ち出し品」といいます。また、ひなんした後、家に取りに行けるようにしておく物を「非常用備蓄品」といいます。

 |
新型コロナウィルス感染症の流行をきっかけに、「非常用持ち出し品」や「非常用備蓄品」に、マスク・消毒液・モバイルバッテリー・体温計などをふくめることがすすめられるようになりました。 |
また、非常食を定期的に食べて、新しいものに入れかえる、ローリングストックに取り組むなど、防災バッグの中身のチェックも必要です。このように、各家庭でも災害に対する意識を高め、さまざまなそなえをしておくことが大切です。
また、災害が起きたとき、どのように行動するのかを、家族で話し合っておくことも大切です。そうすることで、災害が起きたとき、被害を少なくすることができます。
(2)横須賀市の防災の取り組み(公助)

市や県、国の防災への取り組みのことを「公助」といいます。
上の図は、関東大震災と同じような地震が起きた時の予想震度です。横須賀市では、災害が起きたときに安全にひなんするために、市内の地いきごとにハザードマップを作っています。ハザードマップには、災害時に危険な場所や、ひなん所がある場所などの情報がのっています。
その他にも、災害にそなえ、さまざまな取り組みをしています。
 |
津波・洪水・土砂くずれなどによる被害が起こりそうな場所や、そこからのひなんのしかたを知らせるため、ハザードマップを作っています。 |
 |
市内約400カ所のスピーカーで、「防災よこすか」の放送をしています。 |
 |
SNS でも情報を伝えています。 |
 |
災害の種類に合わせて、避難場所の設置をしています。 |
また、災害にそなえ、救助のための訓練をしたり、災害のこわさを伝えたり体験したりするための総合防災訓練を行ったりしています。
 |
 |
| 救助の訓練の様子 | 体験コーナーの様子 |
(3)地いきの人びとの協力(共助)
地いきでの防災の取り組みを「共助」といいます。それぞれの町内では、防災会議を開き、地いきの防災について話し合っています。また、災害時に必要なものを防災収納庫に保管したり、防災訓練を行ったりしています。さらに、各家庭に防災グッズをそろえることをよびかけるなど、各家庭の自助の意識を高める活動も行っています。
 |
防災倉庫には、災害が起きた時に、住民に必要な物が入っています。 |
 |
訓練では、じっさいに発電機などをそうさし、使うことができるかどうかの確認もします。 |
 |
市・地いき住民、学校などが協力して、ひなん訓練を行っています。 |
 |
訓練では、市のしょく員と地いきの人がいっしょに、ひなん所をつくる練習もします。 |
このように、防災の取り組みは「自助」・「公助」・「共助」があります。それぞれの取り組みは、おたがいに協力し合っています。
また、災害が起きたとき、の被害を減らすことを「減災」といいます。「自助」・「公助」・「共助」の取り組みそれぞれを高め、協力し合い、「減災」を目指すことが大切です。
3.学校での取り組み
学校でも、災害にそなえ、さまざまな取り組みがされています。ひなん訓練もそのひとつです。また、災害が起きた時、地域の人が学校にひなんしてくることがあります。その時のために、必要な物がそなえられていたり、ひなん所のルールが定められていたりします。
 |
さまざまな種類の災害が起きたことを考えて、ひなん訓練をしています。 |
 |
小学校にも、水や食料、毛布など、災害時に必要な物がそなえてあります。 |
 |
小学校には、小学生が使うための物とひなんして来た地域の人が使うための物が別々に用意されています。 |
公開日:2023年10月16日 05:00:00
更新日:2025年03月31日 13:24:04