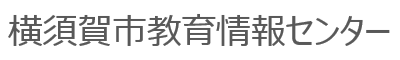カテゴリ:7.くらしを高めるねがい
7.くらしを高めるねがい
| 1.地域に残る伝統・文化 |
| 2.新しく田畑をひらく |
1.地域に残る伝統・文化
(1)横須賀市にある古くから残るもの
横須賀市にも、それぞれの地域に昔から伝わる祭や伝統芸能があります。
| ○ 市内にある古くから残るものには、どのような願いがこめられ、どのように受けつがれてきたのでしょうか。 |

(2)伝統芸能を守り伝えていくために
横須賀市では、一年おきに「民俗芸能大会」が開催されています。市が中心となり、昔から伝えられている伝統芸能をみんなで協力して守るために、また、そうした伝統芸能を残すことで横須賀市の文化を多くの人に知ってもらうために開かれています。
それぞれの地域には、伝統芸能を伝えていくために、いくつかの保存会※があります。その伝統芸能にくわしい人たちが集まって、地域の行事で発表したり、紹介をしたりする活動をしています。静岡県の伊豆から横須賀市の野比に伝えられたとされる「とらおどり」は、保存会の人たちが中心になって、2年に一度発表されています。
| 太田和の獅子舞 | 野比のとらおどり |
 |
 |
※ 保存会…文化・伝統芸能・風習などを伝えるために集まった団体。
◎ 市内にある古くから残るものを守っていくために、わたしたちができることは何でしょうか。話し合ってみましょう。 |
2.新しく田畑をひらく

上の絵は、1907(明治40)年ごろの久里浜(夫婦橋付近)の様子をかいたものです。
この夫婦橋のたもとには、古い石ひが建た っています。この石ひは、今から350 年近く前の1667 年にたてられたもので、およそ、次のようなことが書かれています。
|
「今まで入江※やあれ地だった所を、新しく田や畑につくりかえることができました。しかし、これまでは毎年のように水門や堤防がこわれ、何年も苦労してきました。今後はみんなが幸せになれるよう、神様やほとけ様にお守りいただけるよう、おいのりします。 砂村新左衛門(すなむらしんざえもん)」 |
※海が陸地にはいりこんだ所。
|
今の夫婦橋のようす |
夫婦橋のたもとにある供養塔 |
 |
 |
この石ひにきざまれてある砂村新左衛門とは、どのような人なのでしょうか。そして、なぜ苦労して、入江やあれ地だったところを田や畑に作りかえたのでしょうか。また、なぜ多くの村人がそれに協力したのでしょうか。
―― これらのぎもんについて調べ、考えてみましょう。
| ○ 砂村新左衛門は、どのようにして内川新田をつくったのでしょうか。 |
(1)新田(しんでん)ができる前の久里浜付近のようす
|
江戸時代※1に書かれた本によると、今の久里浜付近一帯は、平作川※2、佐原川、吉井川が流れこむ大きな入江で、そこは、葦などの草木がおいしげる、自然のままのぬま地がつづいていました。 入江は、潮がひく時刻になると、遠く久里浜海岸の方まで砂浜が顔を出し、所どころに、ぬま地や潮だまり(池のようなもの)ができ、潮があがってくると、浅い海になって、今の久里浜海岸につながってしまいました。 この入江の周まわりには、久里浜・八幡、佐原、久比里、吉井 、久村などの村があり、人び 江戸時代は平和が続き、人口が急げきに増えたため、食べ物の不足が大きな問題になっていました。そこで、新たな田畑の開発が必要だったのです。このような開発によってできた新しい田畑を「新田」といいますが、「内川新田」はそのような新田でできた新しい村の名前なのです。 |
 |
 |
__________________________________
※1.徳川氏が江戸(今の東京)で政治を行っていた時代。1603 年から1867 年までをそうよびます。
※2.大楠山のふもとから流れ出し、久里浜港へとそそぐ、三浦半島の中で一番長い川です。
※3.今の金のことで、農家の人々は、主に米をおさめていました。
※4.将軍から、一万石以上の領地をあたえられていた武士のことです。
※5.日本全国の武士を家来にしていた“武士のかしら”です。
(2)工事がはじまるまで
|
砂村新左衛門は、吉田新田※1の開発にたずさわりながら、さらに三浦半島へ足を進すすめました。 そして、平作川など、3つの川が流れこむ内川入江を見て、吉田新田での経験を生かして、田や畑につくりかえようと思いたったのです。 新左衛門は、まず、将軍のゆるしをえて、近くの村の人びとに自分の考えを話しました。村の人びとはその話を聞いて、工事に協力することを約束してくれました。 こうして、1660(万治3)年※2、砂村新左衛門を中心に、久里浜付近の村の人々によって、内川入江の工事が始まったのです。 |
 |
_________________________________________
※1.今の横浜市伊勢佐木町の一帯にありました。
この新田は、そこで商人をしていた“吉田勘兵衛”を中心に開発されたので、そうよばれました。
※2. 1659(万治2)年という説もあるようですが、ここでは、横須賀市史の年表の年をのせました。
(3)新田づくり
| 砂村新左衛門は、まず、吉井の山の下に家を建て、そこに住みました。江戸からうでのたつ職人を何人もよび集め、近くの村からは、自分たちの田や畑をふやそうと、多くの人々がやって来ました。 |  |
|
工事は、まず、海岸にそって、長い堤防をつくり、波が入江に入らないようにしました。 次に、平作川など、3つの川の両側に土手をつくって、いくつにもみだれて流れていた川を、それぞれ1本にまとめました。そして、周りの土地には水路をつくり、土地をかわかしていきました。そして、近くの山から運んで来た土で、田や畑をつくっていきました。今のように進んだ機械などなかった時代なので、これらの作業は全て人や馬、牛の力で工事は進められました。 |
|

|
また、今の夫婦橋があるところまで、高さ1.8m もある長い堤防が作られ、その間には、長さ約10.8m の2つの水門がつくられました。水門は、潮の満ち引きによって、自然に掛け戸が開閉する仕組みになっていました。しかし、台風や津波で大水が出たときなどは、すぐにこわれてしまったり、堤防ごと このように、新田づくりは、自然とのたた |
 |
内川新田からは、最初360石の米がとれましたが、開発が進められ、のちに585石の米がとれるようになりました。

| 砂村新左衛門について | |
|
江戸時代に書かれた本によると、この人は、福井県鯖江市の出身の人で、わかいころから各地をまわり、土木工事や農業などの勉強をしていたそうです。 |
↑正方形の台にみぞがあって、水がたたえてあります。 |

| 「夫婦橋の人柱(ひとばしら)」の伝説 | |
|
内川新田をつくるためにかけた橋も、川が大水になるたびに流されてしまいました。こんな事が何回もつづくと、村の人々の中には、「これは、神様がおいかりであるにちがいない。神のいかりをしずめるためには、人柱(ひとばしら)をたてなければ・・・。」という話が出はじめました。 (田辺悟著「三浦半島の伝説」より) |
公開日:2023年10月16日 04:00:00
更新日:2025年03月31日 13:25:27