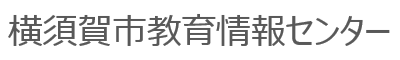-
カテゴリ:民族資料写真
1.机(寺子屋師匠用) -

寺子屋で師匠が使用した机。材質は“けやき”で、どっしりとして風格もある。他に寺子屋が使用した机も当教育研究所で所蔵しているが、材質は“杉”で師匠の机と比較するとだいぶ粗末である。
原寸: 師匠用,たて34cm,横95cm,高さ27.5cm公開日:2023年10月11日 23:00:00
更新日:2023年10月12日 14:13:45
-
カテゴリ:民族資料写真
2.本箱 -
公開日:2023年10月11日 22:00:00
更新日:2023年10月12日 14:14:10
-
カテゴリ:民族資料写真
3.幻灯機 -

幻灯機は江戸末期の嘉永年間、オランダから初めてもたらされた。当初は摩灯ともいわれ恐れられたりしたが、明治時代になると次第に普及していき、明治20年代には静かながら幻灯ブームの一時期を築いた。写真にある幻灯機は、明治初期に使用されたもので、光源は灯油であった。
原寸: 使用時最大の横の長さ77cm,幅22cm,高さ33cm
格納時の横の長さ40.5cm,幅22cm,高さ33cm公開日:2023年10月11日 21:00:00
更新日:2023年10月12日 14:14:22
-
カテゴリ:民族資料写真
4.蓄音機 -

蓄音機は、ターンテーブルを毎回78回転で動かすバネモーターと、音管(アームとラッパ)と雲母の振動板をもつサウンド・ボックスを主要な部品としていた。この写真の蓄音機は、大正末期から昭和初期に出回ったもので、最初は雲母の振動板が使われていたが、その後ジュラルミンに変わった。
原寸: たて45cm,横39cm,高さ35cm公開日:2023年10月11日 20:00:00
更新日:2023年10月12日 14:14:44
-
カテゴリ:民族資料写真
5.大そろばん -

明治時代以降に学校で用いた授業用の大そろばんである。これは、珠が落ちないように軸木に毛のついたもの、細い針金を何本も通してバネのようにしたものなど、工夫をこらしてある。下の5つの珠が4つの珠になったのは、国定教科書4期(昭和8年~15年)からであろう。
原寸: たて31cm,横111cm公開日:2023年10月11日 19:00:00
更新日:2023年10月12日 14:14:55
-
カテゴリ:民族資料写真
6.木銃(ぼくじゅう) -

1886年(明治19年)、諸学校令が制定され、体操科の教材に“兵式体操”として軍事教練が登場した。小学校では初め“隊列運動”といった。1925年(大正14年)、陸軍現役将校配属令及び学校教練要目が公布され、中学校以上では、軍隊から払い下げを受けた銃(単発の歩兵銃)や木銃で、軍事教練を実施した。“木銃”は、主に銃剣術(木銃の先にタンポをつけ、胸に防具をつけてフェンシングのように突き合う)として、使用された。この木銃は、実際の銃に剣をつけた長さに作られている。
原寸: 長さ162.5cm公開日:2023年10月11日 18:00:00
更新日:2023年10月12日 14:15:07
-
カテゴリ:民族資料写真
7.火のし -

炭火を入れてその熱気を利用し、衣服類のしわ伸ばしや形なおしに用いられた。“火のし”の使用については、高田与清(小山田)の「松屋筆記」や山崎美成の随筆「海録」に見られる。江戸時代中期以降一般化したものと考えられる。大正末期頃まで和裁用として欠かせない道具であったが、アイロンの出現で姿が見られなくなった。
原寸: 柄26cm,火入部直径14cm公開日:2023年10月11日 17:00:00
更新日:2023年10月12日 14:15:29
-
カテゴリ:民族資料写真
8.こて -

炭火の中に入れ熱してから、衣服類のしわ伸ばしや形なおしに用いられた。“こて”の使用については、「和名類聚抄」や白石の「東雅」などに散見でき、江戸時代中期以降一般化したものと考えられる。昭和初期頃まで和裁用として欠かせない道具であったが、アイロンの出現で姿が見られなくなった。
原寸: 長さ35cm公開日:2023年10月11日 16:00:00
更新日:2023年10月12日 14:15:40
-
カテゴリ:民族資料写真
9.炭火アイロン -

炭火を入れてその熱気を利用して、衣類のしわ伸ばしや形なおしに用いられた。“こて”“火のし”より効率がよく、大いに普及した。ペリー来航当時の様子を記した松浦武四郎の「下田日記」に、アイロンの絵が見られるので、幕末頃輸入されたものと推定される。洋服の普及と共に、明治中期にはアイロンの発達はめざましいものがあった。
原寸: 横17cm,高さ15cm公開日:2023年10月11日 15:00:00
更新日:2023年10月12日 14:16:57
-
カテゴリ:民族資料写真
10.針箱 -

江戸時代より裁縫は、嫁達の嫁入りの大切な資格とされ、母親やお針師匠寺子屋等でその技術を習得した。1872年(明治5年)、小学校の女児に手芸科がおかれ、ついで1879年(明治12年)発布の小学校教育令で裁縫科が設けられ、以来初等中等教育において裁縫教育は重視されてきた。この写真の針箱は、和裁に必要な道具一式が入れられるようになっており、昭和初期頃まではどこの家庭にも見受けられた。
原寸: たて18cm,横29cm,高さ22.5cm公開日:2023年10月11日 14:00:00
更新日:2023年10月12日 14:17:08